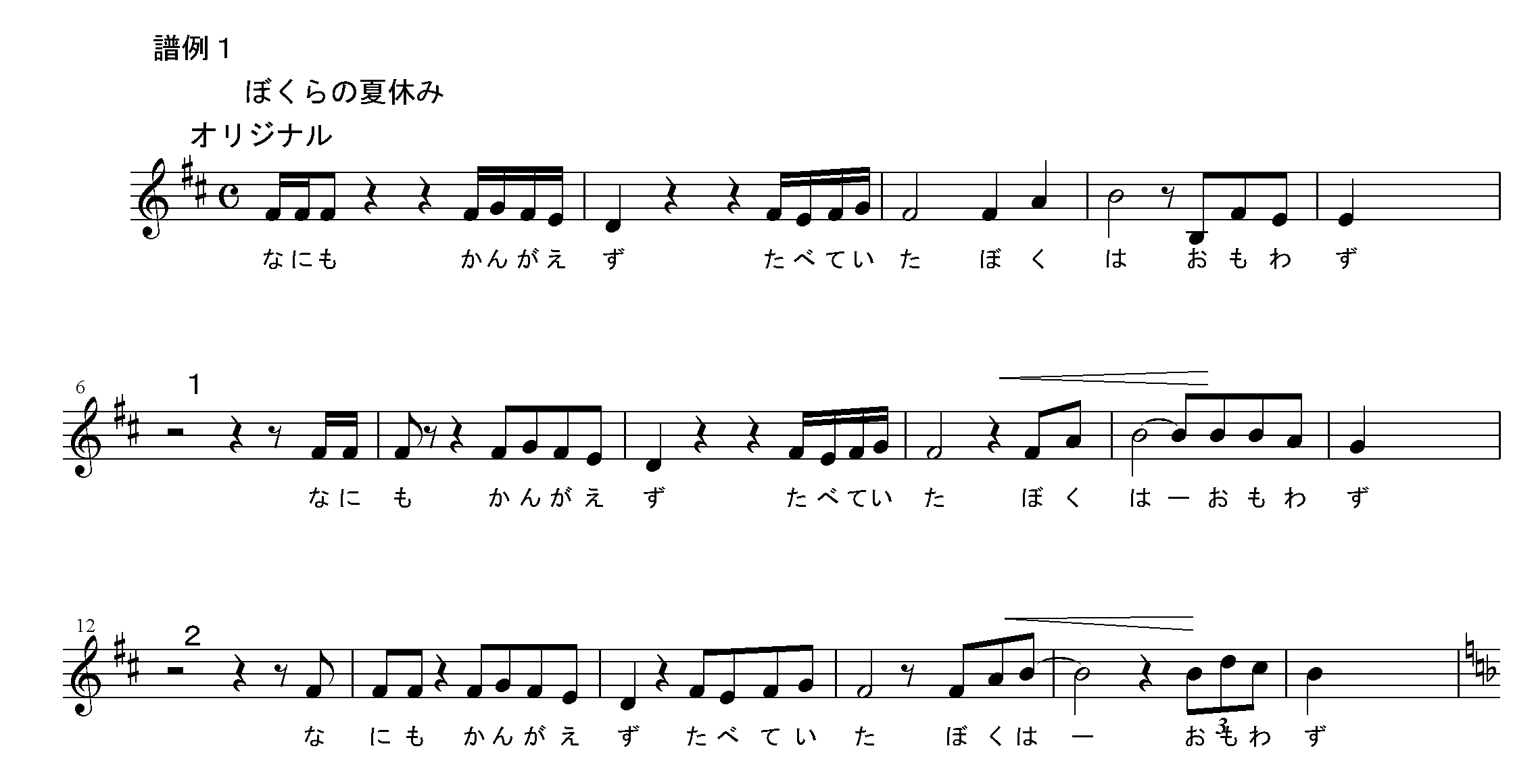
�Q�O�P�R�I���W�i���R���T�[�g�u�]�W
���u�]�҂̗������@
�h�F���^�m�q�@�n�F���������@�r�F�����m�@�s�l�F�������@�s�x�F���`�a�@�@�g�F���c�`�Y�@�@�e�F�����L��Y
�Ȗ��̍Ō�ɂ���y�[�W���̓I���W�i���\���O�u�b�N�̌f�ڃy�[�W�ł�
���T�v�i���������V���f�ځj�@�����L��Y
���N����N�Ƃقړ����T�X�Ȃ����\���ꂽ�B�R�D�P�P�Ȍジ���ƌ������������Ă���k�Ђƕ������e�[�}�Ƃ�����i���ł������������A���ɂ��A�J���E���a�E���̂��E�Ƒ��E�l���E�ӂ邳�ƁE����A�ȂǕ��L����i���W�܂����B�܂��A�Ⴂ�n���������A��Ȃ≉�t�͂̌��������A�����������̂����i�������Ȃ����B
���Ɂu�l�Ƃ��������v�i�������a�@�쎌�ȁj���ے��I���������A�S���n��u�K��i�T�������j�̊w�т̒��Ő��܂ꂽ�����̋Ȃ��A���̌����E����グ�E�ҋȁE���t�����Ȃǂ��o�ė��h�ȍ�i�Ƃ��ăI���R���ɏW�܂��Ă������Ƃ͍���̓������B
�������A�������h��������O�ɁA�`���������Ƃ����̂܂܌��������łȂ��A�ǂ���i������̂��A�ǂ��Ɍ��Ă�̂��A���t�Ɖ��y�łǂ������̐l�̐S�ɓ͂���i�Ƃ���̂��A�n���i���ڂ̍�҂����łȂ����ݏo�����Ƃ��Ă��鍇���c�Ȃǂ��j�ւ̏d�v�ȉۑ�̎w�E�����ꂽ���\��ł������B
�����]�i���������V���f�ځj�@�����L��Y
���N�́A�P�W�s���{���A�R�Y�ʂ���̐��E�ɂ��T�X�Ȃ����\���ꂽ�B��҂̎Q���A���t�̏[���A���O�̑����ȂǁA�n��^���ւ̎��g�݂̑O�i�Ɗ��҂̍��܂����������̂������B�n�암���R�l�ɂ��i��i�s���e���|�悭�A���x�e�ɂ���F�[�v���f���[�X�̐V�����b�c�L�����y�[�����t������A�S�̂Ƃ��Ċ��C�̂���y�����I���R���ƂȂ����B
�Ԃɑ����ď����ł��O�ɂ�����ł������Ƃ����Вn�̎v����g�������������u�ԂɗU���āv�A�������Ԃ̎p���琶����͂�`���u���m�ԁv�A�l�Ԃ�[�����ߕ`�����Ƃ����u�l�Ƃ��������v�݂͂ȍ��N�̑n��u�K��̊w�т̒����琶�܂ꂽ��i�����A�������炸���Ɨ���グ���ǂ���i�ƂȂ����B
�u�ꂿ���ƌĂׂȂ��Ȃ������̓��v�ureason for being�v�Ȃǂ��l�Ԃ����߂鎋�_�̐[�����ƍ�ȉ��t�̎��̍������������B���h�⟭���̌������u�T���V���C���@�V�X�^�[�Y�v��u�����w�e���錾�Q�O�P�R�v�i��҂̓s���œ������t�ł����j�Ȃǂ̖������M�d���B��҂̐h��������`���u�ٗp�u���[�X�v�́A���_���ǂ������ɊȒP�Ɂu�����炵���P����Љ�����낤�v�ƌ��_�t���Ȃ��ŁA�Ɖ���ւ̊��҂��o���ꂽ�B�u�����܂��v�u�W���S���͉̂��v�ȂLj����̂ւ̊��҂������B
�u�t�N�V�}�͏I����Ă��Ȃ��v�͋c�_���ĂB���͂��̂悤�ɂ��������Ȃ��A�̂��Ȃ��A�Ƃ�������������������B����A���̒�����A�ǂ������Ă�����]��l�ԂƂ��Ă̊�����`���̂��B��������̌����������Ƃ��u�Ă���v�ɂ���̂ł͂Ȃ��A�ǂ��������Ƃ��Ē����l�̐S�ɑ厖�Ȃ��̂�`����̂��A�͑�Ϗd�v���B
�܂��A��Ȃ�ҋȁA���t�͂̌���ɂ���āA�����Ă��ĐS�n�悢�`�̐�������i�������Ă������S�Ɏc��Ȃ��A�ƌ�������̂�����B���̋��߂���e�ɉ��y���������Ă��Ȃ���i������B
�n������đn��^���������ɂ��A���Â���ɂ��Ă͓��Ɋw�э��ߍ������Ƃ����߂��Ă���A����Ȃ��Ƃ����������R���T�[�g�������B
���u�]�ɂ������ā@���@�`�a
��
���悢��i�ɂ��邽�߂ɁA�܂����̍�i����̂��߂ɁA�����ł�����`�����ł���Ǝv���ď����܂����B�����h���̕]������܂����A���̈Ӑ}�����ݎ���Ă��������A����͂��͂����������B
��
A�̍�i�œ`���������Ƃ��A�������e�ɂ��Ă�B�̍�i�̂ق��ŏ����Ă��邱�Ƃ�����܂��̂ŁA�ł���Α��̕]�����킹�Ă��ǂ݂��������B
��
����i�ʎ��j�͂����܂Ō����̂��Q�l�ɁA�ł���A���ꂪ�ǂ��ƌ������̂ł͂���܂���B
���ʕ]
�P�@�t���[�_���@�����Ђ��܂��������o�D�P�O�W
�h�F�ۈ牀�̈�����ڂɕ����Ԃ悤�ȁA�y�������A���e�B�[�̂���̎��ł��B�V���v���Ō��t�̃L���������ł��B�搶�̎p���u������ł�v�̈ꌾ�Ŗڂɕ����Ԃ悤�ɓ`���܂��B
�n�F�Ȃ�2�̕�������Ȃ��Ă��邪�A�O���̐��������Ƃ������y�������B�㔼�̓��ȓI�ȕ����͂��ꎩ�̂Ƃ��Ă͂悭�\�����Ă��邪�A�g�[�^���Ƃ��Ă�₭�ǂ��Ȃ��Ă��邫�炢������B�^�C�g���ɏƂ炷�ƁA�O�������𒆐S�ɃR���p�N�g�ɂ܂Ƃ߂��ق����X�b�L������Ǝv����B
�r�F�Ȃɂ��Ȃ������ɂ��̂Ȃ��ɁA�����킹���Ă���ˁB��ۓI�Ȏ��ŁA�G�Ə�ʂ�������ł��܂��B�y�������C���鉉�t�ł����B
�s�x�F�g�����Ċy�����āA�܂Ƃ܂��Ă��邢���̂ł��B���c����̉��y�Ƃ��Ƃւ̃Z���X�̗ǂ��ɂ��킹�A���ǂ������ւ̂��炩�Ȃ܂Ȃ������ӂ�Ɋ�������A���Ă��ȍ�i�ł��ˁB
�g�F�o���ɂ��p�X
�e�F������y�����L���ɂ������ɕ`���Ă��đf�G�ł��B�u�Ȃɂ��Ȃ��`�v���炪���ɂ����ł��ˁB�Ԃɋ��`�ɂȂ�u���߂Ă̕ۈ牀�`�v�̕����A�u�����ӂ�Łv�̉̎���������Ƃ�����Ȃ����A�Ǝv�����ƂƁA�u�����ā`�v�����肩�炿����Ɩ������Đ���グ���`�ɂ��Ă���_�A�������������Ă��悢�Ǝv���܂����B�O���́u��������`�v�̕����Ƃ̑Δ䂪��������o��ƈ�w�\�����������܂�̂ł́H
�Q�@���k�N�����c���ڂ���̂Ȃ₷�݁��o�D�X�Q
�h�F�����̎q�ǂ����������҂����T�}�[�L�����v�̏o���������`�[�t�ɂ��ď�����Ă��܂��B�u���v�H�ׂĂ��v�Ƃ����o�����̈ꌾ�ŁA�[���Ȋ��ŕ�炷�q�ǂ��̎p��\���A���������C�ɉĂ̈���Ɉ�������ł��܂��܂��A���܂��I�@�������e�[�}�ɂ����Ȃ�������������A�����̖ڂŌ��āA�̌��������Ƃ�\������Ӌ`���ĔF�����܂����B�悭��Ȃ��Ńe�[�}�����ڂ������Ƃ��悩�����ł��B
�n�F�����̌���A����юq�ǂ������̒u����Ă�����u���v�H�v�Ƒ����鎋�_�ɂ��āA���������������K�v�B�܂��̂Ƌq�̂Ƃ̋��������̂܂܂ɂ��ĕ\������Ƃ������Ƃɂ��Ă���a�����o����B�Ȃ��u�Ȃɂ��l�����`�v����̃}�C�i�[�E�R�[�h�ɂ��\�����p�^�[�������Ă��āA�����ƌ@�艺����K�v������Ǝv����B
�r�F�V�тƂ��炵�̒��ň�q���ւ̋���������17�l�̗D�����Ăт����ƂȂ��Ă���B�������傤�Ԃ���A�̋Ȃ̃��b�Z�[�W���V�N���B
�s�x�F��҂̌��Ă��镗�i�̊m�����ƒg�������A�����Ɋ������邢���̂ł��B��s�ڂ̂S���߂����ɗǂ��āu���v�H�ׂĂ��v�����Ƃƃ����f�B���҂�����ł��B�����A�P�Ԃɔ�ׁA�Q�Ԃ̉̎��ƃ����f�B�̊W�ɂ͑����̈�a��������̂ŁA�u�������傤�ԁH�v�̂��Ƃ��Q�Ԃł�����x�g���鎍�̍H�v���A�l���Ă������̂�������܂���B�u�������傤�ԁH�j���ł��v�Ƃ��B
�����ɂ���
1.2�s�ځA5.6�s�ڂ̉����͗ǂ��̂ł����A3.4�s�ڂ͂܂��܂����Ȃ̗]�n�����肻���ł��B�u�����l�����A�H�ׂĂ����l�������킸�v���������̒��łǂ������ʒu�Â��Ȃ̂��ɂ���āA�����f�B�[���R�[�h�����Y�����ς���Ă���Ǝv���̂ł��B���̕����A����̉\�����l���Ă݂܂����B�i����P�j
�X���ߖڂ̂悤�ɓ�����P�U���������ˑR�Ɍ����̂́A���Ȃ�V���b�L���O�ł��B���̘A�ň�ԃG�l���M�[�������邱�Ƃ́A���́u�����킸�v�ł͂Ȃ����Ɗ����܂����B�ƂȂ�ƁA����Q�̂悤�ɁA�����Ɉ�Ԃ̎R�������Ă����悤�ȃ����f�B���肪�l�����܂��B�܂��A����̂P�A�Q�̂悤�Ƀ��Y���̐F�X�ȉ\�����ᖡ���Ă݂Ă��������B�H�ׂĂ����̃����f�B�����̂܂܂ɂ���̂Ȃ�A�u�Ȃɂ��v���S���ڂ̗�����o��ق������R�ł��B�P�̂悤�ɁB����͈��ł����A�܂��܂��ǂ��Ȃ�\���������Ă��܂��̂ŁA�`�������W���Ă݂Ă��������B
�g�F�����̎q�������̂�����Ă���Ƃ���ɒz�����������V�N�ɓ`����Ă���B�u�v�킸����Ƃ߂��v�̃����f�B�[�������Ƒ�_�ɐ���グ����u���v����v���炪����ƍL��������悤�Ɏv���B
�e�F������`���Ƃ��A����Ȃӂ��ɐg�߂Ȕ�������̂ɂ��Ă���Ƃ��낪�����Ǝv���܂��B�Ȃ��A�N���]�����N�₩�Łu���v����`�v����̗D�����A���������ӂ�郁���f�B���f���炵���Ǝv���܂��B
�R�@�J�I���������ɔ������o�D�R�S
�h�F�͂��߂̂W���߁u�����̒��ɂ�������E�E�E�v���肰�Ȃ����t�ł����A�S�ɔ���܂��B�����ɘb���̂ł͂Ȃ��W�X�Ƙb�����Ƃɂނ���͂�����ł���̂ł��ˁB�u���{�̂��܂����v�u���{�̗́v�����ˁA�����������ۓI�Ō������₷���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�n�F2�Ɠ��l�ɁA�����̏o������\������ہA���ۂ����̂܂܉̂��Ƃ������Ƃł́u�\���v�Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ���Ȃ��Ƃ������Ƃ�������B���̋Ȃ̏ꍇ�A���̕\���ɂ����Ɛ��Ȃ��K�v�ŁA���Ƃ��Ă̕\���Ɏコ������A���̂��ƂŋȎ��̂̓W�J���U���ɂȂ��Ă���B
�r�F�؎��ȃ��`�[�t�Œ����l���z�����܂���B�����I�łȂ��œ_���i���Ă݂ẮH���A���Ȍ����Ɓg����������h�����o�I�ɕ�����ł���B
�s�x�F��Ȏ҂̌��t�ǂ���A�D���������������f�B�̒�������A�i���錻�������ݏo�Ă���悤�ȁA�e���݂₷���ƂĂ��ǂ��̂��Ǝv���܂��B�����ɂ��đ吨�̐l�ʼn̂��Ă݂����Ȃł��B�֑��ɂȂ�܂����A�����ɏ璷�Ȋ�������̂́A�a�������������炾�Ǝv���܂��B���̒������l����ƁA�a���Ƃf���̊Ԃ����ł͂Ȃ��A���̒��ɏ����ڍs������ɁA������x�u�ӂ����܂̒n�ɂ���`�v���Č������A�C�f�B�A�͂������ł��傤���B���Ƃ��ł����A�u�F����v�̂��ƁAF�R�[�h�𑫏�Ɂu������������߂��ɂ����ʂ��Ă���v������ƁA�u���{�̂��܂������v����̂X���߂͂a�������܂���Db���ʼn̂��A�e�R�[�h���u���b�W�Ɂu�����̒n�ɂ��v�ła���ɖ߂�̂͂������ł��傤���B
�g�F�����Ȃ����t�������Ă��ċZ�ʂ̍�����������B�����A���������ĐS�Ɏc��ɂ����B�S�̋��сE�M���v���E�V���Ȕ������~�����B
�e�F���̕��̕����ւ̎v�������̂܂܂̌`�ʼn̂ɂ��ꂽ�̂ł����A�ŏ��́u�����̒n�ɂ��`�v�̃��`�[�t���ƂĂ��D�����f���炵�������f�B�ƐF�����Ȃ̂ŁA��������ɂ��ď�������ҏW���ꂽ��A�����ƈ�ې[���̂ɂł���̂ł́A�Ǝv���܂��B�u������Ɓv�u���]��Q�v�Ƃ����悤�ȋ�̓I�ȗv�]�����̂Ȃ��Ō����Ă��܂��̂͂��������Ȃ��قǁA�f�G�Ȃ����ɂȂ�Ǝv���܂��B�܂��A�u���{�̍��A���{�̐S�v��������ƈ�a��������܂��B��������̉��y�\���̗͂��f���炵���̂ŁA�ЂƂ̎�����ǂ��̂ɍ\�����Ă����̂��A����邱�Ƃ����߂��Ă��Ă���Ǝv���̂ł����A�ǂ��ł��傤���B
�S�@���u���s�[�X�E�t�N�V�}�����̓����灄�o�D�P�P�S
�h�F�q�ǂ������̌��t�ɂ��A���������݂������������₷���`���Ă��܂��B�܂Ƃߕ�����肢�ł��B�h���b�ł����S�Ԃɋ~���܂��ˁB�������P�`�R�ǂ̃G�s�\�[�h�����ɏd�����̂���ŁA����ꂽ�����ŕ\������ɂ́A���t���炸�ɂȂ�����A�@�艺�������Ȃ����肷��͔̂ۂ߂܂���A���ꂼ���Ɨ������ĐV���ȋȂɒ��킷�邱�Ƃ������ł��ˁB
�n�F�����̌�����ǂ��\�����邩�Ƃ����_�ŁA��͂肢�����̖���������B�o���������̂܂ܒԂ�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A���̊j�ɂ�����̂����Ƃ��ĕ\������K�v������B�������ア���߂ɁA���y�����̃e�L�X�g�ɉ������ĂĂ����Ƃ����`�ɂȂ��Ă����ۂ���B
�r�F�q�ǂ��̐S���������ĐÂ��ɒ�������ȁB�u�炢�Ƃ��ɂ͂炢�ƌ����Ă�����v����ۓI�B���݂��݂Ƌ������ӂ���܂��܂����B
�s�x�F���x�����Ă��[���l���������A�S�ɔ���̂ł��B�����������̒��ɐ����镟���̎q�ǂ������Ɋ��Y���A��҂̒g�����������܂��B���̍�i�����Д��M���Ă��������B
�g�F��肩����悤�Ȍ��t���S�ɓ����Ă���B�R���q�̍��݂̂����Ȃ̂�������Ȃ����A���������f���P�[�g�ȓ��ʂ̕\�����~�����B
�e�F��Ȏ҂ɂ���
�T�@�t�N�V�}����̂��������Ȃ��݁[�����t�N�V�}�͏I����Ă��Ȃ����o�D�P�P�U
�h�F���Ƀ��A���Ȍ��t�Ō��݂̕�����`���Ă��܂��B���Ƃ��Ăނ��o���̌��t�Ɉ��|����܂��B��������ً̋}�ȃ��b�Z�[�W�Ƃ��Ċ������Ă��܂��B���̏d�����b�Z�[�W���������͂����Ɏ~�߂Ď����̕��ɂ��Ă����̂��A���̍�i�́A��̎p�����������₤��i�ł�����܂��B���������グ�Ă���̂����`�ɋy��ł���̂ŁA�i�������������ł��B�������̎���͈�̌���������������̎������Џ����ė~�����ł��B�Ⴆ�Γ����̍���O�A�e�n�̊��d�͂̑O�ł͋��j�̗[���ɖ����ɑ����̎s�����u�t�N�V�}��Y���ȁI�v�Ƌ���ł��܂���B����Ȏp�A�����݂̂Ȃ���ɓ͂��Ƃ����ł��ˁB
�n�F���n�Ŏ��ۂɕ�炵�d�������Ă��鑤����̔��M�ł͂��邪�A���̎��ɂ��Ă���͂�u�\���v�Ƃ����_�ł���ɐ��Ȃ��K�v�ł���Ǝv���B����̍����I�����ł͂Ȃ��A�{��△�O�̍���ɂ�����̂�������̓����Ƃ��ċ�̓I�ɕ\������K�v������̂ł́H�Ȃ��ߑs�������ł͂Ȃ��A����Ӗ��ʼn��y�I�q�ώ����K�v�ł���悤�Ɏv����B
�r�F�����ƂƂ��Ɍ����̃��|�[�g�������������̒��������Ă���B�Q���Ɠ{��̒�Ɋ�]�����ߍ��܂�Ă���B�����������Ƃ������ς��l�܂��Ă���B���Ƃ��낪�ނ������B
�s�x�F���̉̂́A�O���́u�t�N�V�}�͏I����Ă��Ȃ��A�܂��I���Ȃ��v�A�㔼�́u�Ȃ����Č������A�t�N�V�}�͋��ё�����v�̕������c���A���̎��X�ɂ���ĉ̎���ς��Ȃ���A�̂������Ă����ׂ��̂��Ǝv���܂��B������߂Ȃ��ŁA���肩�����Ȃ��ŁA�ȉ�Bb���ɍs���Ă���̉��y�I�ȍL���肪�G��ł��B
�g�F�u�����͏I����Ă��Ȃ��v�̕��������R�[�_�ɂ�����܂ł͑����̐l�̐S���Ƃ炦�邾�낤�B�Q�Ԃ̌�̊ԑt���Ȃ��S�ɋ����Ă���B�����A�O���̌��t�̑����͑i����͂𔖂����Ă��܂��悤�Ɏv���B
�e�F���A���Ȍ���������������e�����A�W�X�ƌ��O������̓{��̍��܂肪�A�Ō�́u�t�N�V�}�͏I����Ă��Ȃ��v�Ɖ̂������ɂ��ׂďW����ꂽ�`�ŕ\������Ă��čI�݂��Ǝv���܂��B�܂��A�Ō�ɓ]�����Ă������u�t�N�V�}��������߂Ȃ��Ł`�v�Ƃ����Ƃ���ɁA�O��ł͏����Ȃ������Ȃ�肢�����߂��Ă��āA���̔������ɂ͊������܂��B�����A�����ɍs�����܂ł����Ȃ蒷���A��������ɂ͂��낢��ƍH�v���K�v���Ǝv���܂��B����Ɋ��҂��Ă��܂��B
�U�@�ǂ������u���U�[�Y���Y��Ȃ����Ȃ������o�D�P�P�O
�h�F��ɐ������F���v���C�������V���v���ȉ̎��ŕ\������Ă��܂��B���t���C�������ʓI�ł��B��ތ^�I�Ȍ��t���C�ɂȂ�܂��A�F�̊�E�p�������Ԃ悤�ȃt���[�Y�������ĉ������B
�n�F�e�[�}�Ɠ��e�����ۓI����ʓI�\���ɂƂǂ܂��Ă���B�`�����Ƃ������̐l���́A���ʂł͂Ȃ����̐l�Ǝ��̂��̂�I�m�ɕ`���o�����ƂƁA���ꂪ�L�����L�E�����ł�����̂Ƃ��ĕ`���K�v������B�Ȃ��A���̐��i������U���ȓW�J�ɂȂ��Ă���B
�r�F���Ȃ���Y��Ȃ��ł͂Ȃ��u�Y��Ȃ����Ȃ����v�̓|�u�����R�ɐ����͂������ă��b�Z�[�W����܂����B�u���Ȃ��v�̎������A�֊s���A�N���ɂ���ЂƂ��Ƃ��ق����B
�s�x�F�L���̕������ɂƂ��Ă͓��ɁA�V�]����̑��݂͑傫���������Ƃł��傤�B�������琶�܂ꂽ���̋Ȃɂ��A���̂��Ƃ��\���Ɍ���Ă��܂��B���y�I�Ɍ���ƁA���̋Ȃ̉ۑ�́u����݂��[�v����̂S���߂ɂ��肻���ł��B���̏����ɂ�����H�v������ƁA���̉̂͑剻���������ł��B�����܂Ŏ����ł����A�t�F���}�[�^�������āA����i��������イ�j���y���~�܂�̂͂��܂�悭�Ȃ��C�����܂��B�܂��A�W�����������ł͂Ȃ��A�C�����i���y�j�̍��܂���P�U�������ŕ\���A�S�̂̃o�����X���l����ƁA���Ƃ��A����Q�̂悤�ȃA�C�f�B�A�͂������ł��傤���H�Ō�̂S�Ԃ��T�Ԃ̂݁A�t�F���}�[�^���g�p���āB
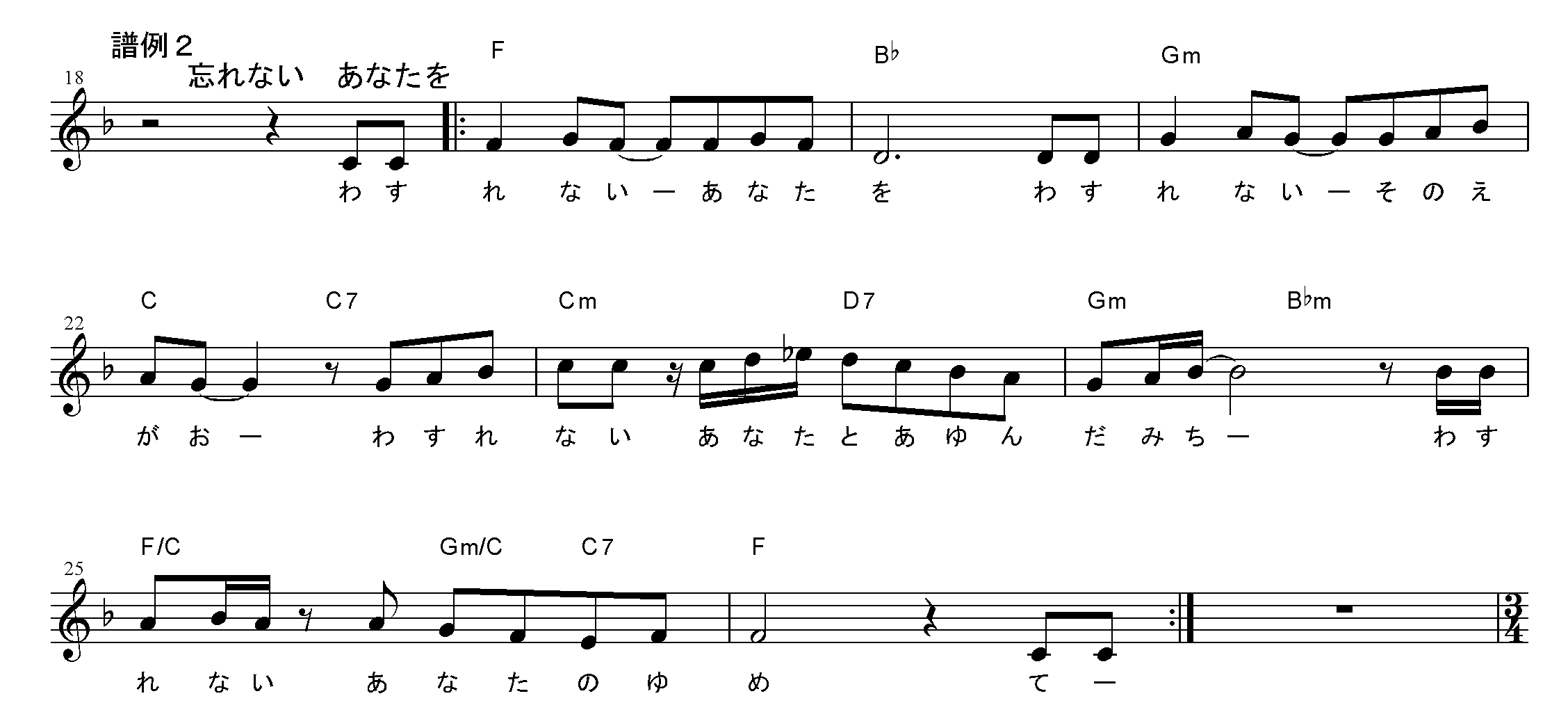
�g�F�̎��̎n�܂肪�����Őe���݂₷���B�����f�B�[�����R�ȗ���Ő���オ�������B�������݂�Ȃʼn̂��Ȃ�A�V���ߖڂ�(�t�F���}�[�^)�͓x�X���Ȃ������ǂ��̂ł͂Ȃ����낤���B
�e�F�����n��u�K��őn�����蒼���Ă���ꂽ��i�A�Ȍ��ȌJ��Ԃ��̒�����F���v���C���������܂��Ă��邢���̂ł��B�@�R�[�h�ł����A3�i��2���ߖڂ̂e/�b�͂悢�̂ł����A1�i�ڂ�3�i��4���ߖڂ̂e/�b�͂Ȃ������Ȃ̂����悭�킩��܂���B
�V�u�k�̍�����v�����c�ƑS���̒��Ԃ������l�G�〈���o�D�T
�h�F�〈��̎l�G�����ꂼ�ꂽ���݂ɕ\�����Ă��܂��B�Ƃ�킯�~�̕`�ʂ��G��ł��B�t�̕`�ʂ������ł��B�Ō��TPP�́E�E�E�̃t���[�Y�͎֑����ȁB�֑��ł����B���̍D���ȉ̂ɐV�������́u�Ìy�����v�Ƃ����̂�����܂��B���̂̍쎌�ƁA�v�m�����ł��B�u�Ìy�ɂ͎��̐Ⴊ�ӂ�Ƃ��A���Ȑ�Ԑ�킽�Ⴔ��ߐ�݂��Ⴉ����t�҂X��v�Ƃ����t���[�Y�����Ɍ����ł��B�Ȃ��悭�A�̂���肢�̂ł����B�l�G�〈��̂P�Ԃ��Ă��̉̂��v���o���܂����B
�n�F�Ȃ̓W�J�͂ƂĂ������B���ɎO�A�������ʓI�Ɏg���Ă��āA�L�т₩�ȕ\���ɂȂ��Ă���B�����A���̓��e�����X�g�́uTPP�͋����Ȃ��v�ɋ����Ɏ��ʂ���`�ɂȂ��Ă��āA������Ɩ���������B����������������K�v������̂ł́H
�r�F�悭����グ��ꂽ�ȂƉ��t���B�j���̐����������肵�Ă��ċ�����L���ɂ��Ă���B�ւ莩���̋ȑz�������Ɖ����o���Ă������̂ł́H
�s�x�F�����f�B�Ƃ��ƂƂ̊W��R�[�h�̓��������R�ŁA�̂���Ɏ��ꂽ�������܂��B���킢�̂��邢���̂ł��ˁB�Ō��TPP�������Ă���̂ɂ́A�^�ۂ������ꂻ���ł����A���́u�ǂ��������v���Ǝv���܂��B�Ȃ��Ă���̉̂Ƃ��Ă܂Ƃ܂��Ă��܂��B
�g�F���y�̌i�F�∤���悭�\�����ꐮ����ꂽ�ȂɎd�オ���Ă���Ǝv���B�����A�������{���y��ւ�ȂNj��ɔ�����̂��~�����B�Ō�̌��_�����˂Ɋ�����̂͂��̂��߂ł͂Ȃ����낤���B
�e�F�I�V�����ʼn̂��₷�������n�\���O�ł��B�s���ɂ��s���ɂ��L����Ǝv���܂��B�u�s�o�o�`�v�͂����Ō���Ȃ��ق����A�Ǝv���܂����A�ǂ��ł��傤�B
������C�����̂������o�D�U
�h�F���ʂ̂Ȃ����t�ŁA��������\������A�悭�܂Ƃ܂�����i�ł��B�u�c�������̊C�E�E�E�n�������̋�E�E�E�v�ĊO�肸��̂������t�Ȃ̂ł����A���̍�i�ɂ͂��̌��t�̕K�R��������̂ŁA�����Đ����͂�����܂��B
�n�F��1�����f�B�����p�^�[�������Ă͂�����̂́A�����ȂƂ��ĂƂĂ��悭�܂Ƃ܂��Ă��āA�Ȃ̓W�J�����R�Œj���Ə����̑Δ���I�݁B���t���ɂ����ЂƍH�v����ƁA�Ȃ̓W�J����莩�R�ɂЂ낪��������Ƃ��ł���悤�ɂȂ�Ǝv����B
�u��v�̃A�N�Z���g�ɂ���a�����o����B
�r�F50�l���鐺�̃n�[���j�[���[���ӂ邳�Ƃւ̈���`���Ă����B�u�c�����v�u�n�����v�̏d�w������łB
�s�x�F����ł�����̂ŁA�����ɂ����̂ł����A�����̂��ł��܂����B�g���C�J�����c�̊F����̔M�ӁA�肢�A�{�肪�����������ʂ��Ǝv���܂��B�������������܂ł��q�ǂ������Ɏc����悤�ɁA���Љ̂������Ă��������B���ق����ł͂Ȃ��A�S���̐l�����ɁA���ꂼ��̒n�������ĉ̂��Ăق����Ɗ肢�܂��B
�g�F�o�����̖₢��������ۓI�B���̌�̉̎�������ʓI�ɂ��v���邪�A����͂���Ƃ��Đ�������悭����ꂽ�Ȃ��Ǝv���B���t���͉��B
�e�F�ŏ��̖₢�����Ǝ��̌��ӁA�����čŌ�̌Ăт����Ƃ���3�̕�������ۓI�ɍ\������A�z�����[���̂��Ă��đf���炵���Ǝv���܂��B���t�����̉̂ɂ�����v������������Ɠ`�����̂ł����B�S���e�n�ŁA���ꂼ��ɂ��������̍�肪�����߂��邱�Ƃ��t�N�V�}�ɂȂ���̂��Ǝv���܂��B
���ԂɗU���ā��o�D�P�O
�h�F�Ԃɕ����ւ̎v����������G��ł��ˁB���̌���ʂ��̂Ɍ��t�ɂ�����傫�ȗ͂����邱�Ƃ��A���ՂȌ����ł��܂��\�����Ă��܂��B�Ԃ��L�[���[�h�ɂ����̂��������Ă���Ǝv���܂��B
�n�F�����f�G�ŁA���̎���ɂӂ���݂�����A��炵���c�ސl�тƂ̉��������Â������`����Ă�����̂�����B���y�����̂ق�����Ƃ������������݂��C�������ƂȂ��`���Ă��đf�G�B����17���ߖڂ́u�فE��E��v�u�ЁE�ƁE��v���X�^�b�J�[�g�ʼn̂��悤�ɍ�Ȃ��Ă���Ƃ��낪���Ɍ��ʓI�ň�ې[�����̂�����B�����25���߈ȍ~�̓W�J���L���ȍL��������������Ă��Đ[�����ɋ������̂�����B�ƂĂ��f�G�ȋȁB
�r�F���������Ȏ��Ƃ���Ɍ��������₳�������Ђ������ȁB�u�����������܂��ցv����ۓI�őN�₩�ł��B
�s�x�F�Ȃ������ł����A�������t�ł����ˁB�̎������̎�����u���������O�ցv�ƏC���������Ƃ��A���̋Ȃ����g�߂Ȃ��̂ɂ��Ă���C�����܂��B�Ȃ͂���ƁA�R�̕����Ƃ�G�̉��𒆐S�Ƃ��������f�B�ŁA�Ƃ�����ƃ����n�����Ȃ��Ȃ�̂ł����A���̉̂͂��ꂼ�ꃊ�Y��������Ă��Ď咣������A�S�̂��܂Ƃ܂��āA���܂��ł��Ă��܂��B�̂���̃Z���X�̂悳�������܂��B
�g�F�l�̒g���������݂��݂Ɠ`����Ă���₳�����ɂ��ӂꂽ�ȁB�Ō�̕����u�Ԃ͏Ί�v�����͉��x�J��Ԃ��Ă����̓x�ɍL����Ƌ������������͂��������̂��Ǝv���B���x�����t���d�˂���x�ɐ[�܂��čs���Ȃł͂Ȃ����낤���B
�e�F�����n��u�K��ł��D�]�������ȁA����̒��ł̔����A����������đf�G�ȉ̂����܂�܂����B�����A�����W�ł���Ɏv�����[���\�����ꂽ�Ǝv���܂��B�Ō�̂ق��A�u�ԂɗU���v�̕����A�u�Ԃ͏Ί�v�Ɠ������A�����R�[�h�ł����A�u��v�̏��߂��`��A�����e���Ƃ��ăA�����W�����ق������L���肪�o��̂ł́A�Ǝv���܂����B
�W�@������v�ƒ��Ԃ������l�̊肢�����Ȃ��Ă����������o�D�P�Q�Q
�h�F��҂̏����ǂ���̏_�炩�ȗD�������t�̉̂ł��B�����Ђ������錾�t�A������錾�t�i�L�[���[�h�j���Ȃ̂ŕ�����̒��Ɏc��ɂ����ł��B���w���̖l�̎p���͂����肳����H�v�������Ƃ悢�Ǝv���܂��B
�n�F���̓��e����]�ƌ��т������̂ŁA���ꎩ�̂Ƃ��Ă͎��̕\���Ƃ��Ă͈����Ȃ��̂����A���̊�]���u�������肽���v�Ƃ������Ƃ��́u��������ׂ��v�Ƃ������ƂɏI�n���Ă��āA���̐l�Ȃ�ł͂̃��A���e�B�Ɍ�����B�Ȃ����������u��������ׂ��v�Ƃ������肳�ꂽ���e�ɉ��������̂ɂȂ��Ă��ĒP���ȋ����ŏI����Ă���B
�r�F�u���������݂̂Ȃ��ł˂ނ��Ă��܂��v�u�K���X�̂킽�̂䂫���ӂ�v�̑N�₩�ȕ`�ʂ����ɟ��ށB�u���܂����`�v�ւ̔��ɂ����ɂȂ���̂��A�ނ������Ƃ��낾�B
�s�x�F�����̂��ł����Ǝv���܂��B�����f�B�Ɖ̂̍��������R�ł������łȂ��A���ɔ�����̂�����܂��B�K���X�̂킽�́A���炪���ɂ����ł��ˁB��C�ɂȂ���2�ӏ��A��ڂ͂R���q�ɂȂ�Ƃ���A�����͕��ʂɁA�P���x��łӂ邳�Ɓ[�Ɖ̂��ق����������ȂƎv���܂��B�����ƂS���q�̒��ŋ}��3���q�ɂȂ�̂ŁA�̂̒��ɂ��郊�Y�����o���h������āA�u����H�v�Ǝv���Ă��܂��̂ł��B2�ڂ͏I�����Ȃ̂ł����A���̓}�C�i�[�ŏI��肽���ȂƎv���܂����B
�g�F�����Ȏ��_�ʼn̂����Ƃ̑�����C�Â����Ă�������B
�e�F�����䂦�ɑ{�����邱�Ƃ��ł��Ȃ������A���������]���҂�����������̂ł��ˁB���̖��Ɍ��ꂽ���w���̎v����\���̂ɁA�ŏ��ƍŌ�́u�������Ȃ����Ă��������v�Ƃ������t�͂������ĂȂ��ق����i����͂����̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���܂��B����Ȃ��Ă��\�������邭�炢�`����Ă�����e���Ǝv���܂����A�ǂ��ł��傤���B�܂��A���̕����ɂ���ꂽ�d���C�`���C�d���C�a�V�Ƃ����J��Ԃ������̂܂܂ł͒P���ɂȂ��Ă��������Ȃ��Ȃ��Ƃ����C�����Ă��܂��܂��B���̒��ԕ��������ƕ`������łЂƂ̍�i�ɂ��Ă݂����ƁA�ڂ��͎v���܂����B
�X�@�l�Ƃ��������������l�Ƃ����������o�D�S�R
�h�F�[���ŁA�l��������̎��ł��B�e�[�}�ɂ���������g��Ŋ�����������i�ŁA�����x�������ł��B���̒n����̐����̈�Ƃ��Ă̐l�Ԃ̘����������߂�̎��̓V���v���ŕ�����₷���A������ɃX�g���[�g�ɓ͂��܂��B
�n�F�g�l�Ƃ͉����h�Ƃ����e�[�}�ɑ��āA������ʓI�ȃR�g�o�Ō���Ă��āA���̕\���Ƃ��Ĉ�ʘ_�ɏI�n�������e�ɂȂ��Ă���B���̂��߁A���y���Z���̒�^�Ō�邩�����ɏI�n���Ă���B�e�[�}�ɑ��āA���̏�������Ȃ̏�������A�g���͂����v���h�Ƃ������̐l���g�������Ă����Ȃ��Ŋ��������̂������Ɨ����ɕ\�����Ă����K�v������̂ł͂Ȃ����B
�r�F���j�[�N�Ȑ�����B��n�A���ׂ̂����A���̂��̂����сA�Ƃ��݂̂�����B���t�A�t�B�j�b�V���̐��̂Ђт����[���������ɐ����͂������ē͂����B
�s�x�F�T���Ɏ����ꂽ�����Ȏ킪�Ă̊Ԃɂ������A�D�ꂽ��i���ł�������܂����ˁB���t�⍇���A�����W�����炵���ł��B�R�Ԃɂ����镔���̉��y�I�Ȕ��W���A�ƂĂ��ǂ��ł��Ă��܂��B������x�����Ă݂����̂ł��B�֑��ł����A�R�Ԃ̂��̂��Ƃ����ɁA�q�g�Ɓ[�ƍs���A�C�f�B�A�����肻���ł��B�ԑt�����������Ă��Ȃ̂ŁA�b���t���������ł����A���̊ԑt�̉��f�ނ̏�ɁA�q�g�Ɓ[��̃����f�B���ڂ�\�������肻���ł��ˁB����Ȃ��Ƃ܂ōl�������Ă�����i���Ǝv���܂��B
�g�F�ƂĂ��_��I�ȋ����B�[���Ƃ���Ől�ԎЉ�́u�ɉh�v�Ɍx����炵�Ă���B�A�����W���f���炵���B�s�A�m�̊ԑt�Ɉ������܂��B�R�Ԃō������W�J�����Ƃ��Ɏ���ƌ��t�������ɂ����Ȃ�̂́A���t�̖��Ȃ̂��A����Ƃ��A�����W�ŃJ�o�[�ł���̂��낤���B
�e�F�����n��u�K��Ŕ��z���A�L����Ɛ[���Ɗi���̂���f���炵����i�Ɏd�オ��܂����B�f��̃^�C�g���o�b�N�ɂ��Ȃ肻���ȃC���[�W�̍L����Ȃł��B�s�A�m���t��A�����W���f���炵���A����グ�Ă���ꂽ�w�͂ɔ���ł��B
�P�O�@�r��̂��������c�����_�R���o�D�R�W
�h�F�u�⓹��o��ƁE�E�E�E���_�R�������ꂽ�v�Ƃ����o�����͈�ې[���A����������������o�R�҂̂悤�Ȃ������ɂ����Ă���܂��B�r�W���A���ȉ̎��ň��������Ă��܂��B�Ƃ�킯���������̕����̉̎��͔������`�ʂ����ʓI�ł��B�G��ȍ�i�ł��B�����Ďw�E����Ȃ�A���_�R�̗Y�傳��\�������b�����������R�����悤�Ɋ����܂��B�u�R���������Ă���ƂĂ��Ȃ����͂Ŕ����Ă���v�ł͗҂����ł��B�]�k�ł����A��������̏��́u���������v�͊������ł������ł����A�����R�̗Y�傳�����ɕ\�����Ă���Ǝv���܂��B
�n�F�`�ʓI�����ƍ����ȂƂ��Ă̐����W�J���I�݂ł͂��邪�A�����̂��̂����_�R���牽���ǂ��������̂�����̓I�ɓ`����Ă��Ȃ����ǂ�����������B���̂��߁A�ȂƂ��Ẵ��A���e�B��������ʓI�Ȃ��̂ɂȂ��Ă��Ďc�O�B
�r�F�n���ł́u���_��܁v�i�y���薼�j�ƌĂ�Ă���̂ł��傤���B����ꂽ�ȂƉ��t�ɍ��������������B������Љ�łȂ��A��i�ƈ،h�̏d�w�������l��O�������Ȃ��B
�s�x�F�L�O���ׂ��P�O�O�Ȗڂɂӂ��킵�����ł��B�S�̂�ʂ��āA���_�R�̃X�P�[���̑傫��������ʂ��Ėڂɕ����Ԃ悤�ł��B���ɂS�W���߂���̉��y�I�ȍL����A�܂��A�U�U���߂���̂��ƂƉ��̊W���ƂĂ��悭�ł��Ă���Ǝv���܂����B��̘A���i�Ȃ������j�ɍH�v������܂����A���ʂɏ������ق������₷���ł����A�X���[�łȂ���҂̈Ӑ}���킩��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�g�F��̃e�[�}�ɂ�����葱����̂͂������B�R�D���̐l�ɂ͋����ł���ȂȂ̂ł��낤�B�t���[�Y��������Ɣ���ɂ����̂ŋȂ̓W�J�������ɂ��������B
�e�F�ŏ�������K�ԍ��c�܂ł͎R�̕��i�������Ȃ���N�₩�ɕ����яオ���Ă��܂��B�����A�d���炻�̐i�s���~�܂��Ă��܂����悤�ɓW�J���͂����茩���Ȃ��Ȃ�̂��c�O�ł��B
�P�P�@�q���[�}���E�t�@�[�}�[�Y���]�����o�D�R�V
�h�F�E���E���A�T���T���A���N���N���̈ӎ����Ďg�����I�m�}�g�y�����ʓI�ł��ˁB�V���v���ȉ̎��ł����^�C�g���ɍ��߂�ꂽ�u�]���v�̔O��^�������ɓ`���܂��B�Ō�̂��т̕������Ȃ��ł��ˁB�u�����Ȃ����˔\�͍������~�蒍���v�͌��t�̗]�C�ƃ����f�B�[�ɗ���������悤�ȋC�����܂����A�����Ă��ė������Ȃ������ł��B
�n�F�J���g���[�E�~���[�W�b�N���̃e�C�X�g�ɂ��ӂꂽ�Ȏ��́A�d���e�[�}���̂��\�����@�Ƃ��Ă͂悭�H�v����Ă��āA�����͂Ȃ��B�ނ��낱�������A�v���[�`�̂ق����A�����̐[��������������Ɠ`����Ƃ����_�ňӖ�������悤�Ɏv����B�t���[�Y�`����1���ڂ��O�A���ŋL�����Ă��邪�A���t���ƎO�A���ōׂ����L����������A�������������������������ŏ������ق����ǂ��̂ł͂Ȃ����B�܂�1����1��Ƃ����悤�Ɋ���U��K�v�͕K�������Ȃ��悤�Ɏv���܂��B
�r�F�s����]���B�Ђ����܂������t�B�u���܂̓N���������Ƃ��Ȃ��v�ɏœ_���݂��B
�s�x�F���x�������Ă݂܂������A�ŏ����������Β����قǖ��킢�������A��҂̎v���A�肢��{�肪�`����Ă��邢���̂��Ǝv���܂��B�S�Ԃ܂ł̉̎������܂������f�B�ɂ͂܂��āA�悭�ł��Ă��܂��B���Ƃ��Ȃ�����̂S���߂͓��ɋ��ɋ����܂��B������x�����Ă݂����Ȃ̈�ł��B�L���ł����A�R�A���ƕt�_�ƕ����Ă��܂����A���ʂȂ�����肪�Ȃ���A�ǂ��炩�ɓ��ꂳ��Ă������̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�g�F�[���ȃe�[�}���y���^�b�`�ŁA��������т����E�Ȃ���������`����Ă��閡�킢�̂���Ȃ��B�����Ȃ��~�葱�����˔\�ւ̓{������߂ĉ̂������Ƃ��낾���u���˔\�́v�̃t���[�Y���������Ă��܂��B�����ɉ���������Ȃ��������Ă��܂��B
�e�F�y�������Ă������Ƃ����Ȓ���z�����܂������A�ӊO�Ƒ��߂ł����B��������������A�Ƃ��������ł��B�u�E���E���v�u�|���|���v�ȂǕ��ʂ̌��t�ł͕\������Ȃ�������A�l�X�ȋ[���ŕ\������Ă���Ƃ���ɁA���̋Ȃ̖��킢���o�Ă��܂��ˁB�ƂĂ��D���ȋȂł��B�u���̎R�̌������։_�͗���Ă����v�Ƃ����Ō�̃t���[�Y�������Ă��܂��B
�P�Q�@�����̊C�̎������c���F�悠�肪�Ƃ����o�D�P�P�P
�h�F����܂Ŏx���Ă��ꂽ���ӂ̋C�������S�҂ɖ������̎��ł��ˁB�����c�O�Ȃ̂́A�ތ^�I�ȉ̎��������A�F�̎p�������Ă��Ȃ��ł��B���A���e�B�[�̂���̎����~�����ł��B�u��̉Ԓ��v�Ƃ������X�͑f�G�ȋ�Ԃł��傤�ˁA���̘b�����荞��ŗ~�����ł��B
�n�F�Ȃ͑O���̝R��I�Ȑ����iA�j���ƂĂ����R�ŗǂ��̂����A���ԕ��i�����o���Ȃ��^�������ǁ`�j�̒Z���ʼn̂�������iB�j���������ތ^�I�Ȑ����ɂȂ��Ă��Đɂ����B�g�݂�Ȃ̏Ί�`�h��̐����iA�f�j����₭�ǂ��������Ă��܂��̂́A����B�ȍ~�̉��y�W�J�ɕK�R�����Ȃ����߂��Ǝv����B���������āA���̍\��������������������K�v������Ǝv����B
�r�F�o��̒��ɂ���l�Ɛl�Ƃ̂��������������t�ɂ悭������Ă���B�u�݂�Ȃ̐S�ɂƂǂ��v�́u�݂�Ȃ̐S�ɂƂǂ��v�ƌ������Ă����������B�u�₳�����F�v�̎������������肷��H�v������E�E�E�B��������Ƃ��������ꂽ���t�ɒ����������B���肪�Ƃ��I
�s�x�F�F�ւ̐S����̊��ӂ̋C�������A�̂̒����炵�����芴�����܂����B�\���Ȃǂ��ǂ��܂Ƃ܂��Ă���Ǝv���܂��B���Ƃƃ����f�B���҂�����ł����A������Ƃ���ꂽ�s�A�m���t���������ł��ˁB
�g�F�����Ȃ��悭�܂Ƃ߂��Ă���Ǝv���̂����A�܂Ƃ܂肷���Ĉ�ʓI�ɂȂ��āA�c�O�Ȃ��炢���ȏ�i��G�s�\�[�h�����܂蕂����ł��Ȃ��B
�e�F�u���肪�Ƃ��v�Ƃ����S�̂���������ϔ������ȁB�T�^�I�ȋN���]���̂܂Ƃ܂����`�ł��܂��ł��Ă��܂��B����ɏ����Ă���R�����g�̓��e����ꂽ������ƋȂ̈�ۂ��L���ɂȂ�Ǝv���܂����B
�P�R�@�R���p�@DE�@�킩�������ٌ`�̂Ƃ�ځ��o�D�P�O�S
�h�F��ې[���^�C�g���ł��ˁA���ʓI�ł��B����ɔz�����ꂽ�I�X�v���C���U���H�̃g���{�ɗႦ���̂ł��ˁA��肢�I�@���������������I�X�v���C���Ɖ���悤�ɂȃt���[�Y���������ق����e���Ǝv���܂��B������ɂ���������`���Ǝv���܂��B
�n�F�g6���̉H���̃g���{�h���炱�ꂪ�I�X�v���C���w���Ă��邱�Ƃ͗e�Ղɗ����ł��邪�A���̓W�J�������܂�̃p�^�[���ŁA�Ō�ɂ́g�͂��ȁh�ɋA������Ƃ����̂������ɂ����ՂɊ�������B�Ȃ��σ��Z���ŁA������`���̒�^�p�^�[���ł���A���y�ői������e�́g���܁A�ǂ����Ă��h�Ƃ����K�R�����\���ɓ`����Ă��Ȃ��B��^�p�^�[����˂��j����̂��~�����B
�r�F�u�ٌ`�̂Ƃ�ځv�̈Úg�������s�C�������`����Ă����B�������[�����t�̒��ɗ͂Â悳������B
�s�x�F�����̂��Ǝv���܂��B�R��ڂɏ��߂āA�ٌ`�̃g���{���Ӗ����邱�Ƃ��킩��܂����B�i���������e�[�}���ƍŏ��͎v���܂����B�j�ŏ��Ɍ���Ă��牉�t����ꍇ�͕ʂƂ��āA���������⑫�̐������v�邩������Ȃ��ł��ˁB�Ō�́A�����ȁA�ʼn������Ƃ��낪�a�V�ň�ۓI�ł��B���y�I�ɂ́A���Ƃ��u���̂��v�̕������R���ʼn̂��ꍇ�A�j���������f�B��Bb�̉��ŁA������Gb�̂ق���������������܂���B�e�[�}���傫���̂ł����A��₠������ƏI����ۂ�����A�Ō�́u���̎q��ɂ����v��A�u����v�́A�Q��R��ƌJ��Ԃ������Ǝv���܂����B
�g�F����Ȃ���ӊO����������薼�����Ɋ�ȓW�J�����҂��Ă��܂����̂����A���܂łɂ悭�g���Ă����앗�Ȃ̂ł�����Ǝc�O�B�����A���̂悤�ȃ^�C�����[�ȑ�ނɃ`�������W�������邱�Ƃ͑厖���Ǝv���B�S���߂��ƂɈ�̃t���[�Y�𐬂��Ă���悤�Ȃ̂�����nj㔼�́u���̂����������v�������R���߂����Ȃ��̂�������a���������Ă��܂��B
�e�F�I�X�v���C�ւ̍����́A���̃^�C�g������悭����킳��Ă��܂��B���Ɂu��邷�ȁv�ƒf���Ă���Ƃ��낪�����ł��B�u���̂����������v�̕���������^����͂����A3���߂ň��肵�Ȃ��܂��ɓ���Ƃ��낪�悭�H�v����Ă���Ǝv���܂��B
�P�S�@�S�R�s������@�Ђ܂ȃX�^�[�Y�������D���@���{���D�����o�D�P�O�U
�h�F�I�[�����̗ǂ��A�y�������������낤�Ƃ����ӗ~���̎��ɕ\��Ă��܂��B�������~���肷���̋C�����܂��B���������n����������āA�@�艺�����ق��������Ǝv���܂��B�������Ƃŕ\������̂������Ǝv���܂��B�P�`�R�Ԃ̗��ꂩ�炷��ƁA�S�Ԃ͂����������˂ł��A���_�̔���肷�����Ǝv���܂��B
�n�F���̖����A�����A�|�\����D�荞���ł͂��邪�A���̂��ƂƁA�Ō�̃t���[�Y�Łg�u�N����v�͉S���Ȃ��^
�����Ǔ��{���D���h�Ƃ������傪�[�����т��Ĕ[���ł���悤�ȓW�J�ɂȂ��Ă��Ȃ��B���������āA�Ȃ̓W�J���P���Ŏc�O�B
�r�F�t���I�Ɉ����ւ̒�R�����Ă���B���݂��݂Ƃ����i���B�y�߂̃R�~�b�N�I�ȋȂ�������������Ȃ��B
�s�x�F���ƂƉ��y�����a���āA���y���܂Ƃ܂��ėǂ��ł��Ă���Ǝv���܂��B�̂��₷���ł��ˁB���ƑS�̂̍\���͍čl�̗]�n�����邩�Ǝv���܂��B�R�Ԃ܂łŏI���̂ł���Ȃ�A����͂���Ŋ��^�̂Ƃ��Ă����Ǝv���̂ł����A�S�Ԃŗ��J������A�N����̃e�[�}���o�Ă���̂ł���̂Ȃ�A�^���ʂ�������Ɛ[���@�艺���Ȃ��Ƌt���ʂɂȂ�댯������܂��B�������l���A�N���オ�̂��Ȃ����ǁA�܂�����͂���Ƃ��āA�̂悤�Ɉ��Ղɑ����邱�Ƃ̂Ȃ��悤�ɁB���߂Ă��Ƃ��t�ɂ��āA�u���{�͍D�������njN����͉̂��Ȃ��v�ƏI���ق��������Ǝ��͎v���܂��B
�g�F�e���݂₷�������f�B�[�B���̑g�ݍ��킹���o�����X�悭�A���Ƃ��ǂ��낪�c�{�Ă���B�u�N����͂������Ȃ��@�����Ǔ��{���D���v�̂Ƃ���ł͋��̂����v��������B���t��ł�◝���������������f�B�[���������肷�邪�A������ċ����ł���̂ł���B
�e�F�����荞�݂̎��̃C���[�W���炷��Ƃ����������邭�e���|�̂��郁���f�B��������Ǝv���܂��B4�Ԃ͂�����Ƃ��̉̂ňꏏ�ɉ̂��̂͂��������Ȃ��A�Ǝv���܂��B����Ȃ��Ă��킩��܂��B�u�N����͂������Ȃ����ǁA���{�͍D���v�Ƃ����L�[���[�h�ł܂��ʂ̉̂�n�����ق����悢�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�C���g���Ɋ}�ؓ�����́u���̓��̎��Ɓv�̍Ō�̕����������Ă��Ă���̂�4�Ԃւ̕����ł����H
�P�T�@�V�w�l�R�[���X����Ƃ��Ɓ����̓��������Ɓ��o�D�P�O�T
�h�F�k�Ђ̋ꂵ�݂̒����痧���オ����X�̎p�������A�K���ӂ邳�ƂɋA�낤�ƃG�[���𑗂�̎��A�R���p�N�g�ɂ��܂��܂Ƃ߂Ă��܂��B��������ۂ��c��ɂ����ł��B�q�ǂ������A���t����̐��A�p�����������@�艺���ď����ė~�����ł��B���т̕����ɐ����͂������܂��B
�n�F�`���悤�Ƃ�����̂͂Ȃ�ƂȂ��킩�邪�A���ꂪ������ʓI�Ȏ���ɂ��\���ɏI����Ă��āA���ǂ��������c��B�Ȃ������������傩����Ă��鋿���Ƃ������̂��������Ȃ��B�����Ƌ�̓I�ɁA�����ĉs�p�I�ɕ\�����������ƁA�`���������Ƃ����グ�Ă����K�v������Ǝv���܂��B
�r�F�l�ւ̈�����[�����t�ɂ��߂Ă���܂����B�悭�܂Ƃ܂��ă��b�Z�[�W���`����i�ł����B
�s�x�F�̂��₷���āA�悭�܂Ƃ܂��������̂ł��B��ȃe�[�}�ł���A��҂̂܂Ȃ����̕����ɂ��������܂��B�����A���Ȃ��Ƃ��̓����}�������u���v���A���ЂƂ�̓I�ɂ悭�����Ȃ��C�����܂��B���y�I�ɂ́A�u���܂���������ǁv�́u���v�̏����̎d���͓���ł��ˁB�H�v�̗]�n�����邩������܂���B�������̂��Ƃ̃����f�B�t��������l���Ă݂܂����B
�i����R�j�ǂ��炪�������͂킩��܂��A���Q�l�܂łɁB
�g�F�P�D�Q�D�R�Ԃ�ʂ��ďI���̂S���߂������ՂɊ����Ă��܂��B�k�Ђ⌴���̔�Q�Ɍ��������Ƃ��A�\�l�\�F�l�X�Ȏv�����������邾�낤�B�䂦�ɍ���͋ꂵ�݂������Ȃ��猾�t�A�����f�B�[���i��o���Ă��邱�Ƃ��낤�B�s�\����������Ȃ������葱���邱�Ƃ���Ȃ̂��낤�B
�e�F�����オ�낤�Ƃ��錈�ӁA�v������Ȃł��B�����f�B������ɋᖡ������グ����[�݂������ƂłĂ���Ǝv���܂��B���Ɋe�R�[���X��4�i�ڂɂȂ�Ō�̕����ł��ˁB
�P�U�@�Ê�̂��ƂŁ��l�o�[�M�u�A�b�v���o�D�P�Q�S
�h�F�����c�̖��O�ɒp���Ȃ��A�V���v���Ŗ��̂���̎��ł��ˁB����ȑf�G�ȃe�[�}�\���O������Ή̂����Ƃ��y�����Ȃ�܂��ˁB���ɂP�Ԃ��D���ł��B�u�Ȃ���������܂����v�̌��t�͒j�炵���Ă����ł��B�P�A�Q�ԂƂR�A�S�Ԃ̓j���A���X����Ⴄ�̂ŋC�ɂȂ�܂����B
�n�F�̂ɂ��뎍�ɂ���A�ЂƂ̎��ۂȂ茻�ۂȂ�s���Ȃ���A���̂܂ܕ\������Ƃ������Ƃ��ЂƂ̕��@�_�ł͂��邪�A���ꂪ�\���s�ׂƂ��ĈӖ��������߂ɂ́A��͂��҂̎��_�Ǝ咣�Ƃ������̂����m�ɕ\������Ă��邱�Ƃ��K�v���Ǝv���܂��B���ꂪ���̉̂���͏\���Ɋ������Ȃ��B
�r�F�l���̕��݂����ݍ��܂�ė͋������͂̂��鉉�t�ł����B�u�������C�ɐ����Ă������v�ɂނ����ăe�[�}������グ���Ă���B
�s�x�F�Ê�Ƃ͎v���Ȃ��A���C���ӂ�邷�Ă��ȉ��t�ł����B�����́u�����v�ɂ��������܂����A�ꐶ�́u�ꏏ�v�ɂ��ʂ��Ă��܂��ˁB���ɂ҂�����̃����f�B�ŁA�悭�ł��Ă���Ǝv���܂����A������s�A���ƂS���߂��炢�����āA�������������ω�������ق����A�Ǝv���̂͗~����ł��傤���H�P�Q���߂̏I��ɂ͔����L�����B
�g�F�o���₷���݂�ȂŐ������킹�₷���Ȃ��낤�B�����A���܂荪���̂Ȃ��M�҂ɂ́u�Ȃ�����v�Ƃ��������ʼn�����R��������B�P�Ԃ͗ǂ��Ƃ��Ă��Q�ԂŁu�����ʼn̂��H�v�Ƃ����݂���ꂽ���Ȃ��Ă��܂��B
�e�F�P���Ȃ���Ŋo���₷�����C���o��̂ł��B�u�Ê�v�͒ʉߓ_�ŁA��������܂����C�ɂ����[�Ƃ��邼�A�Ƃ����ӗ~�ɂ��ӂ�Ă��đf���炵���ł��ˁB�u�ꐶ�v�͊y���ʂ肤�����u�ꐶ�v�ƕ������܂����A���t����Ă���悤�ɂȂ�Ɓu�ꏏ�v�ɂ������Ă��܂��ˁB�܂��A2�i�ڂ�3�i�ڂ������h�̉�����n�܂��Ă��܂����A2�i�ڂ́���n�܂����ق���3�i�ڂ̔����͂����������悤�ȋC�����܂��B
�P�V�@�Ƃ��ǂ��V���K�[�\���O���C�^�[���ƌj�����u�w�e�v�錾�Q�O�P�R���o�D�W�X
�@�@�i�G���g���[����Ă��܂������A���ƒ�̎���ɂ��}����Q�����t�ł��Ȃ��Ȃ�܂����B�j
�h�F���{�l�̉̂������Ȃ��Ďc�O�ł����B�����ʼn̎���ǂ��Ă��邾���ł��ʔ����ł��B���Ƃ���̉̂ł͈ȑO�u�N����v�k���u�����ĐH�ׂ��ł����v�ƕ����Ă�����ɑ�����܂����B����Ő��g�̐��k�ɐڂ��Ă���搶�ɂ��������Ȃ��b���A�Ɠ��̃��[���A�ł����Ə����Z���X�̗ǂ��B�E�X�ł��B
�n�F���������ւ��̂Ƃ����̂́A�����Ǝ��݂��ėǂ��Ǝv���܂��B�u�֔��錾�v�̑ւ��̂Ƃ��āA���̓��e���ɗ�ŁA����ɉ��݂������āA�ƂĂ��ʔ����B�Ō�́u�������������v�Ƃ��u��߂����悤�v�Ƃ������傪�A�S�̗̂��ꂩ�炷��Ƃ��ތ^�I�ɋ����̂��ɂ����B
�g�F��X�̒m��Ȃ������A���ɕ`����Ă���̂ŁA�̂ŕ����Ȃ��Ďc�O
�e�F�ڂ��̋��E�������c�ł��������Ă݂悤�Ǝv���܂����B���������������̂���������~�����ł��ˁB�ł�����ԑt�����̃����f�B���A�������낢�J��Ԃ��̃L�[���[�h���l���āA�킹���Ȃ����A�Ȃǂƍl���Ă��܂��܂��B
�P�W�@�`�V�w�l�R�X���X�R�[���X�����Ԃ��Ă��������o�D�S�V
�h�F���[���A�̃Z���X�ɕx��ŁA���������Ƃ��Ċy�����̂ł��B�P�Ԃ͏��C���̂悢�����肪���������ł��B���̌�̓W�J�����ł��B�R�Ԃ́u�E�E�E�킽�������ɂ݂͂̂��߂�v���킩��ɂ����̂ŕʂ̕\�����čl���邱�Ƃ����߂��܂��B
�n�F�ȂƂ��Ắu���Ԃ��Ă������v�̌��C���ӂ�鋿���̂ق����V���v�������悭�܂Ƃ܂��Ă���B�u���a�̃����i�[�v�̓����f�B���C�������s���R�ȂƂ���ƁA�I�~�`�ɂȂ肻���łȂ�Ȃ��Ƃ��낪�����āA���y�I�ɂ��A���o�����X�ȂƂ��낪�U�������B���C�͂�Ƃ������t�ł͂��邪�A���������Ƃ��������������������ƁA�����Ɠ`�����̂��ӂ����ł����Ǝv���B
�r�F�R�X���X�R�[���X�̔N�ւ����炩�ȉ��t�ł��B���t����������Ɠ`���B
�s�l�F�T�[�N���̃e�[�}�\���O�Ȃ�ł��ˁB�݂Ȃ��y������������Ă���l�q���ڂɕ����т܂��B�u�����Ȑl���W�܂�Α傫�ȗ͂�����v����Ȃ��������Ƃ�������ƌ����Ă���Ƃ��낪�����ł��B�Ō�́u�ˁI�v���₳�����Ă܂������ł��ˁB
�s�x�F�����ǂ��l�����Ă��āA��ۓI�Ȃ����̂ł��B�I���������ɂ����ł��ˁB�A�����W�E���t�ɂ�����ł��B
�g�F���������̎v������������l�ߍ��̂͂ƂĂ����͂����ӂ�Ă���B���h���[�ɂȂ��Ă����̂ň�Ȃ��������Ƃ�����蕷���Ă݂����B
�e�F�u�֒����g������D���I�v�Ƃ����̂Łg���܂�h�ł��ˁB���炵���I�y�����R�[���X�̃e�[�}�\���O�ł��B�ŏ��́u�R�X���X�R�[���X�v�������̃R�[���X�̖��O�ɂ���Ό��\���Ă͂܂�Ƃ���͑����̂ł́H
�����a�̃����i�[���o�D�S�W
�h�F���a�̃o�g�������̐���Ɏ�n�����Ƃ�����|�̉̎��ł��B�킩��₷���A��肭�܂Ƃ߂Ă��܂��B�u�n�����悲����E�E�E�v�̕����A���������ތ^�I�ȕ\���Ɋׂ��Ă��܂��B���������@�艺�������t������Ƃ����ł��ˁB
�n�F��L�L��
�r�F�w�i�ɂ��銈����������ł��܂��B�̂��y�����̃o�b�N�{�[�����`����Ă��܂��B
�s�l�F�^�C�g�������C���[�W�Ɖ̎��̓��e�ɂ�����ƃM���b�v�������܂��B������u���a�v�Ɓu�����v�����Ԃ��Ăڂ₯�Ă��܂��Ă���悤�Ȋ����ł��B�i�荞�����悩���������m��܂���ˁB���͂��܂������f�B�ɂ̂��Ă���Ǝv���܂��B
�s�x�F�F����̕��݂�肢���Ïk���ꂽ�̂ł��ˁB�u�ł��v����̉��y�̕ω��ƍL��������ʓI�ł��B�B��A�u�q�ǂ��������k���Ă�v�̕����͍ċᖡ�������Ƃ�����������܂���B�����ƈ�ۓI�ʼn̂��₷�������f�B�E�a���������Ă���\��������܂��B
�g�F��ɋL�q
�e�F�C�i������A�D�����Ƌ������������̂ł��ˁB�A�����W�������ł��B�u�����[�v�̂Ƃ���ɂ͂܂���������̂ł��傤�B���҂��Ă��܂��B
�P�X�@�����c�k�������肪�Ƃ����o�D�T�O
�h�F����̃I���W�i���R���T�[�g�ŁA�͂����萳�ʂ��猛�@�X�����̂����̂͂��̍�i�������Ǝv���܂��B�X�����e�[�}�ɂ����̂̍X�Ȃ�n�삪�����߂��Ă���̂��Ǝv���܂����B�L�[���[�h�u�푈��m��Ȃ��@����͍K���v�A�C���p�N�g�̂��錾�t�ň�C�Ɉ������݂܂��B�悭�܂Ƃ܂�����i�ł��B
�n�F�����͝R��I�łƂĂ��f�G�����A�ЂƂ̎�肩��Ȃ��Ă��邽�ߕω��ɖR�����A���x���������@���J��Ԃ���邽�тɃ}���l�������Ă�����_������B�`����B�ɑ��������肪����ƁA�Ȏ��̂������ƈ������܂�Ǝv����B���t���C���̎���u���肪�Ƃ��^9���^����͌ւ�v������܂ł̎���̌��_�Ƃ��ď�����Ă��邾���A��⋭���Ƃ������A�ϔO�I�ŁA���Ƃ��Ă̕\�����p�^�[�����������̂ɂ��Ă����ۂ�����B
�r�F�Ђ����܂����\���̎��B�����������镽�a�ւ̊ɐ����͂�����B
�s�l�F�^�C�g���������ł��ˁB�X���ւ̊��ӂ����݂��߂Ȃ��畷�����Ƃ��ł��܂����B�P�ԂQ�ԂR�ԂƂ��Q�s�ڂ̉̎��������Ă���Ǝv���܂��B
�s�x�F���͍̉̂���̃I���R���̒��ł��A���ʂɈ�ې[���̂ł����B�e�[�}���������Ƃ͂������ł����A�O���̉̎��ƃ����f�B�E�x���̊W�����炵���̂ł��B�u�x�����̂��Ă���v�̂ł��B�����A�u�����Ƃ��Ȃ����v�܂ł͂��炵���̂ł����A�u���ɂ��Ă���邩��v���炠�Ƃ́u�ɂ����I�v�Ǝv���܂����B������C�Ɋ������Ă��܂��ƁA�u�푈��m�炸�ɖl��͕��߂�v���Ƃ̂Ȃ�Ƃ��傫�Ȋ�т��`���Ȃ��̂ł��B����Ǝv���Ȃ��珑���܂����A�u���肪�Ƃ�����v�Ɍ������āA�����ƐS��h���Ԃ�A���W���Ă��������f�B���Ȃ��ł��傤���H�@���������ƁA�����Ɖ̂��p����Ă����̂ɂȂ肻���ȋC�����܂��B
�g�F�̎��̒��Ƀ����|�C���g�g�߂Ȑl�̋C�z�Ȃǂ��C���[�W�ł��錾�t������Ƃ����Ɛe���݂₷���̂ɂȂ�̂ł͂Ȃ����낤���B
�e�F��ۓI�ȏo�����̃��`�[�t�u�푈��m��Ȃ��@����͍K���v�ƁA���肰�Ȃ�������Ƃ��낪�����ł��ˁB������u���ɂ��Ă����v�Ƃ������������D���ł��B�\���Ō����Ɓu���ɂ��Ă���邩��v�ŏI��炸�ɁA���̎��̕��������}�ɂ���悤�Ȏ����čs�����ɂ�����Ǝv�����̂ł����A�ǂ��ł��傤�H
�Q�O�@���S�r�܃^�[�~�i�������c�����܂ł��i�E��̎�҂����Ɂj���o�D�T�P
�h�F�E�ꂩ�甭�M�����̂������X���ɂ���̂ŁA�M�d�ȍ�i�ł��B��y���Ⴂ���Ԃɒ������������Ȃ܂Ȃ����Ɋт��ꂽ�D���x������i�ł��B���X������҂̎p����肭�\������Ă��܂��ˁB�ŋ߂��܂蕷����Ȃ������Ȃ��Ȃ����u�J���҂̘A�сv�ՂȌ��t�Ő^�������ɓ`���Ă���܂��B
�n�F���y�̍��ł݂�ƁA3�̓��@�i�����̒P�ʁj����Ȃ��Ă��邪�A�ŏ��iA�j��8���߁A���iB�j��4���߁A3�ԖځiC�j��8���߂Ƃ����\���ɂȂ��Ă��āA��͂�B�̕����������ƖL���ɂӂ����ł����Ƃ����Ɨǂ��Ȃ�̂ɂƎv����B���̂���C�̓��t���C���ɑ������邪�A���ꂪ��₭�ǂ���ہB�����������y�W�J�����A���o�����X�ɂȂ��������́A��͂莍�̍\���ƓW�J�ɂ���Ǝv����B�E��̉̂炵�����e���̂��Ă��邾���ɐɂ����B
�r�F����𖾗Ăɕ`���āA���t�����������Ƃ��Ă���B�E��̎�҂��Ƃ炦��܂Ȃ������������������B�u�킩�������v�̕����́A�ȂɍH�v�������Ă��E�E�E�B����ʂ��銴���B
�s�l�F���邭�e���|�悭�������Ă��܂������A���̂��Ƃ�������ƃA�_�ɂȂ��ĉ̎����������ɂ��������ł��B16�������̃A�E�t�^�N�g�i�܂�t���[�Y�̓��j���������ɂ����̂ł����S�̂̈Ӗ�����x�����������ł͂Ȃ��Ȃ�������Â炭�Ȃ��Ă��܂��Ă���̂��c�O�ł��B���V�A�̋ȃh�i�G�t�X�L�[�́u�S�H�v���C���[�W������y���ȃs�A�m���t�͑f�G�ł����B
�s�x�F�Ȃ������ǂ��܂Ƃ܂��Ă��āA�o���̊W�����R�ŁA�̂���Ɏ��ꂽ�������܂����B���Q�l�܂łɂł����A�R�[�h�ŁACm�ADm�iD7�j�Ȃǂ��g����ƁA���y�����������L���ɂȂ�Ǝv���܂��B���Ƃ��A����₩��Cm�@�Ȃ�����F7�@�@���킷����Dm�@�̂悤�ɁB�������ǂ����͕ʂł����B�O���̉̎�����⑽������C������̂ŁA�������������Ƃ���Ƃ��K�v��������܂���B
�g�F�E��̎Ⴂ���Ԃ����ւ̈���������邳��₩�ȉ́B�E��̖��邢���������炵���D�������Ă�B
�e�F�w��̃e���|��葬�������͎̂��Ԃ̊W�ł����H������Ƃ��������Ƃ��Ă��܂��A�̎������܂��`�����Ȃ������̂��ɂ����ł��ˁB�܂��A4�i�ڂ����}�ɂ����Ă��Ă��܂����A5�i�ڂƂ̊W�����������Ȃ��Ǝv���܂����B5�i�ڂ�4�i�ڂƓ����C���[�W�ŌJ��Ԃ��̂悤�ɂ�����A�Ōオ�L����A���Ă��ȐE��\���O�ɂȂ�Ǝv���̂ł����B
�Q�P�@�`�������W���[�Y��reason for being���o�D�T�Q
�h�F������Ӗ������x���Ƃ�������̎��A���ۓI�Ȃ̂Łu�ڂ��v���l�Ԃł���̂��A����ȊO�̂��̂Ȃ̂����f���ɂ����ł��B�u�ڂ��v�����q�͂ƍl����Ɨ��������̂ł����B���ꂢ�Ő������ꂽ���t�ł��A�ł��ӎ��̕\�ʂ�������Ă������̂悤�Ȉ�ۂ�ۂ߂܂���A�����ЂƂ��ݍ��\�����ق����Ǝv���܂��B
�n�F�Ȃ̍��͂ƂĂ����ꂽ���̂�����A����������̂�����B���ꂾ���ɁA�����₢��������̂����ɓ����ƂȂ��ėp�ӂ���Ă���̂��A�Ƃ�������ۂ��o����B�܂�A�u�����Ȃ�낤�Ȃ��v�Ƃ����W�J���A���̒ʂ�ɉ̂��Ă����A�Ƃ������ƁB����͂���łƂĂ����x�ȋZ�@�ł͂��邪�A���������\�蒲�a�I�ȕ\�����炿����Ƃ͂��ꂽ�̂Ƃ������̂ɂȂ�ƁA����ɖʔ����Ȃ����Ǝv����B
�r�F���Ȃ̑��݂Ƃ��̂��ւ̂��Ƃ����݂��[���Â��ȃ��b�Z�[�W�ƂȂ��Ă���B�ЂƂ�̏��N�̖ڂƐS��ʂ��ĐS�̎p��������ł���B
�s�l�F�������t�ł����B�����̃A�����W���f�G�ł��B�`���̉̎��Ƀh�L�b�Ƃ������܂��B�u�l�����܂ꂽ���̓��@�N�͉���������̥���v�����ł����u�N�v�Ƃ����̂́A�u�l�v�̗��e�̂��ƂȂ̂ł��傤���B������ɂ�������Ɠ��e���l�������鎍�ł��B�܂��Ɂu�A�i�^�m���G�n�v�ł��ˁB
�s�x�F��ې[���̂ŁA���t�������܂߁A�悭�ł��Ă���Ǝv���܂����B�u�ڂ��v���N�Ȃ̂��A�P�ɁuI�v�Ȃ̂��A�������̂��̂������Ă���̂��A�킽���ɂ͓ǂݎ��Ȃ��̂ł����A���̈Ӗ��ł́H���c���̉̂ł�����܂����B�l�I�ɂ͓�����҂́u�l��̐S�̒��Ɂv�����D���ł��B
�g�F���̋Ȃ̍��ꂽ�w�i����������̂��ȁH�B���ۓI�Ȃ��ǐg�̉��ŋN�����Ă��邢���Ȃ��Ƃ�z�������Ă���鋻������������̂��B
�e�F��ۓI�ȃ^�C�g���Ɖ̂ł��ˁB�u�ڂ��v�͒N�Łu���݁v�͒N�Ȃ̂��B���������Ȃ����ƂŃ~�X�e���A�X�ɕ������܂����A�u�����߁v�u�c�u�v�u�u���b�N��Ɓv�u�����v�ȂǑz�����܂��B
�Q�Q�@����l�̓W�[���Y�����D�����l��̐S�̒��Ɂ��o�D�T�T
�h�F�������ɖ������̎��Ő����čs����Y��\�����Ă��܂��B���t�Ƀ��A���e�B�[���s�����Ă���̂œ`���ɂ����ł��B�Ȃ��L�̒������邮��܂���Ă���悤�Ȉ�ۂƌ��������̂��i���̕��͂����ۓI�ł��ˁE�E�E�j�B�ł��Ō�ɂ͖����Ɍ������p�������Ă��܂��A����̌��������܂��B�]�k�ł����A�O���[�v�̖��O�ɂɂ��ȂݑS�����W�[���Y�œo�ꂳ���̂��ȂƊ��҂��Ă��܂�����B
�n�F����\���������̂��A����`�������̂����ǂ����͂����肵�Ȃ��B����͎��̏����莩�g�̂Ȃ��ł͂����肵�Ă��Ȃ����ʂł�����悤�Ɏv����B���������āA�Ȏ��̂͂�����x��^�p�^�[���ŃR�g�o�����ɂ��邱�Ƃ͂ł���Ƃ��Ă��A���y�Ƃ��ē`����Ă�����̂��ア�A�Ƃ�����ہB
�r�F��]�����肠�����Ă���B���R�Ƃ̌𗬂�����ł���B
�s�l�F�N�����̍��Ə����ւ̊�������]�ɕς��čs�����Ƃ���E�C���f���ɂ����ɍڂ��ĐS�̒��ɂ��݂킽���Ă��܂��B���ԓI�Ȑ�����C�ɂ��Ă����������̂��Ǝv���܂����A1�Ԃ��������������ł��B�A�����W�����͓I�ł��B�N�̑升���ŕ����Ă݂����Ȃ��B
�s�x�F�̂������̂ł����A���t���ǂ������ł��B�����������悤�ȃ����f�B�ɁA���������Ƃ����܂��ڂ��Ă��܂��B�\���Ɉ�̉̂Ƃ��Ċ������Ă���Ǝv���܂����A�t�ɂ܂Ƃ܂肷���Ă��āA��ۂ������Ȃ�댯������̂�������܂���B�����Ȃł����A�S�̂̃o�����X���l���Ă��A�u�Ȃ��Ƃ������̂��ƂA����Ȃɂ��S�߂Ȗl�炪�v�̕ӂ�́A�ʂ̉��̐F�i�f�ށj���ق����C�����܂����B�i���x�𗎂Ƃ��Ƃ��A�����}�C�i�[�ɂ���Ƃ��B�j���y�̗͂��L���ɂ���̂ł�����A�����������f�B�̒��ł��A�ǂ������y�I�ȃ`�������W������Ƃ����̂�������܂���B
�g�F�����Ȃ�����Ȃ�ɂ܂Ƃ܂��Ă���̂�����ǁu�N���܂������̂��v�u�ǂ�Ȍ��t���ނ̔ޏ��̐S���Ƃ炦��̂��v���ꂪ�����Ă��Ȃ����ǂ�������������B
�e�F�u�����̋L���v�Ƃ���������O�łȂ��L�[���[�h�����ɁA�m���Ȃ��́A������Ӗ��A���������Ƃ����N�̐S�݂̍�l���������`����Ă��܂��B�ureason for being�v���l�A�s�v�c�Ȗ��͂������Ă��܂��B���t�����͓I�ł����B
�Q�R�@�����Ŋo���郍�V�A��u���u�h�D���[�W�o�v���R�D�P�P�ߌ�����̕��݁��o�D�T�W
�h�F���[���V�A����͑��ʓI�Ȋ��������Ă݂���̂ł��ˁA�����܂����B���߂ē����{��n�k�ƕ����������̂̐^����
�E�ɔ��M���邱�Ƃ̑�����������܂����B�̎��͒Z�̂��v�킹��Z���e���X�ŁA���ɂ܂Ƃ߂Ă��܂��B�Z�����t
�͉s���荞�ޗ͂�����܂����A���̕��[�܂�Ɍ����邱�Ƃ�����܂��B
�n�F�����o���������̂܂܃R�g�o�ŒԂ�����Ԃł���A���I�C�}�W�l�[�V�����Ɍ�����B���̂��߁A���y�����V�A���w�̃p�^�[���P�����`�œW�J����Ă��āA�ӂ����ł����Ȃ��B�����̉��t�����Ȃ艹���������A�c�O�Ȍ��ʂƂȂ����B
�r�F�d���e�[�}�����t�ɒu��������B�w�i�ɂ�������̉f����������ł���B�u�ς��ɑς��@�J��M�����݂�O�ցv�ɋ����B��߂���O�߂̌����B�l�߁E�ܐ߂̈ӎv�ւƔ��W�B�����Ƀp���[��������B
�s�l�F�Z�̌�ɍ�Ȃ����ꂽ�̂ł��傤���B���̊W���Ȃ��Ƃ��v���܂����A�������������ł͂킩��Â炢�������ɂȂ��Ă����������܂��B�l�X�i���ނ��イ�j�A�e�q�i���₱�����j�A�l���픘�i�ЂƂ����Ђ��j�ȂǁB�r�܂ꂽ���Ƃ̃f�B�X�J�b�V�������\�Ȃ�ǂ��Ɍ������ĒN�Ɍ������Ă������̂���b���������ƂȂǂ�������������܂���B4�Ԃ́u�ς��ɑς��v�Ȃǂ͎��͌��������Ȃ��t���[�Y�ł��B
�s�x�F�͋������t�ł����B���\����j���ł̉��t�ɂӂ��킵���Ȃ������Ǝv���܂��B���y�Ƃ��čl����ƁA�uM�X�̋���Ȓn�k�v�Ȃǂ��̎��ɓ��ꂸ�ɁA���̂��ƂŒu����������@������Ǝv���܂����B���o�Ă���D�̂��́AA���̕����ǂ��ł��傤�B
�g�F���̃e�[�}�ł̑n��̓����������B�͂邩�ߋ��̏o���������ݖ����ɓ`����̂ł͂Ȃ��B���N�����Ă��邱�ƂŁu�N�ɉ���`���̂��̂��H�v�܂��܂����s���K�v���낤�B
�e�F���[���V�A����炵�����V�A�I�ȃX�P�[���̑傫�Ȃ��肾�Ǝv���܂����B�Z�̂̋Ïk���ꂽ���t�̈ꌾ�ꌾ�ɂ��郁���f�B�́A��͂�Ïk���ꂽ���̂��]�܂�܂����A�悭�l�����Ă���Ǝv���܂����B�O���̊i���̍�����4�Ԉȍ~�̌㔼�ɂǂ����W�����邩������ł��ˁB
�Q�S�@�����N���ҍ����c���t�E�O�����o�D�U�P
�h�F��Ђ������k�ɂ悹��v����^���ɕ\������Ă��܂��B�t�̗l�q�����������ތ^�I�Ȃ̂��C�ɂȂ�܂����B�̋��̏t�ɑ���v��������������������ŗ~�����ł��A�Ⴆ�Ζ�R�œE�ݑ��������L���A�����炬�̉����ł��傤���B�O���̐[�܂�ŁA�㔼�̌��ӂɐ����͂����܂�܂��B
�n�F�^�C�g���ɍ��߂�ꂽ�v���Ƃ����̂͗����ł��邪�A���ꂪ�T�O�I�ȕ\���ɂƂǂ܂��Ă��āA�����ЂƂ�̐��Ɍ�����B���̂��߁A�u�t�͂܂������v����u������
���͕��ށv�ւƓW�J����Ƃ���ɊϔO�I����������B���y������܂ł̃n��������u�ł� ���̓�����v�̕����Ńn�Z���Ƃ��A�u������`�v����σz�����Ƃ��ēW�J����Ƃ�����،^�ł���̂��c�O�B
�r�F�O���̏�i�ɂ݂��݂������������ėU�����܂��B�u�O���v�̎��d���Ӗ������肰�Ȃ����R�A�g�߂Ȃ������܂�����`�ʁB�u�E�E�E�܂��v�̌h�̂ɍ��߂�ꂽ���S�B�u�ӂ邳�ƂɁ@�t�͂܂������v�Ɨ͂�ł��Ȃ��B�㔼�́u�ł��v�u������v�͗v���ӁB�A������Ɨ������O�ɂł�B�Ȃɑ����Ă��悢�̂ł͂Ȃ����B
�s�l�F�Z����������̂c.�b.���ْ����������Ă���܂��B�������͒Z���������C���킸�W�X�Ƃ�����������S�ɐ��݂���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�s�x�F��҂̎v���E�肢�ɋ������܂��B�����ɔ������t������Ă�������A�S����킽�����肢�܂��BC��Cm�ւ̓]�������܂��ł��Ă���Ǝv���܂��B�u�͂�[�͂�[�v���A�����`�ŒZ���ɂ���̂����ʓI�ł��B�O���A�J��Ԃ��̂��ƂȂǁA�O�Ƃ͕ʂ̘a���i�F�j���g����̂���̃A�C�f�B�A���Ǝv���܂����B���ʂӂ��聨Em�@�͂遨Am�@�ȂǁB
�g�F�D�����\���Ő[���v�����߂��Ƃ���ɂ��̖̉̂��͂�������B�����炱�����قǂ̒Z���ɂȂ铱�����������܂���i�ɍ\���Ȃ��������v�����`���̂ł͂Ȃ����낤���B
�e�F�ق�Ƃ��̏t�̓������肢�Ȃ�����A�܂��܂������t�B�`�ɂƂ���Ȃ����R�Ȃ���ł����B�P�`�R�i�����ׂāu�\�v�ŏI����Ă��܂����A2�i�ڂ��I�~�`�ɂ��邱�ƂŁA3�i�ڂ́u�͂�`�v�̕������V�N�ɋ����Ǝv���܂��B�ǂ��ł��傤�H
�Q�T�@�����c���̓����ڂ��O�ŗV�т����ȁ��o�D�U�W
�h�F�q�ǂ��̎��_�Ō������̂̐[����Y��\�����Đ������Ă��܂��B�q�ǂ��̃��A���Ȍ��t�ɂ͐����͂�����܂��ˁB�u������肱�킢�v���܂��I�@1�ԁ`3�ԂւƏ�ʂ̓W�J���ƂĂ����ŁA�G��ȍ�i�ł��B�]�k�ł����A���m���̐^�@��J�h�̎Ⴂ�V��������{���̎q�ǂ������̌��t�ɍ�Ȃ����u�e�c�i�M�}�[�`�v�Ƃ����̂�����܂��B�i�}�X�N���Ȃ����@�O�ɂ̓R���C���ۂ�����j�Ƃ����̎�������܂��B���̉̂ɋ��ʂ�����̂�����܂��ˁB
�n�F�����Ȃ��͂�Ƃ����\������������́B�d���������̂��Ă��邪�A���̏d���˕Ԃ��p���[����������B���Ɂu�_���_���_���_���v�̕��������Ƃ��Ă��V�N�ŁA�ȂƂ��Ă����Ɍ��ʓI�ȋ����ݏo���Ă���B�ɂ����̂́AA�|B�|A�f�̓W�J��A�f���Ɨ������y��̂悤�Ȉ�ۂ�^���邱�ƁB�����炭�ԑt�̃s�A�m�p�[�g������������ۂ����߂Ă���悤�Ɏv����B�������������������Ȃ�����A�S�̂Ƃ��ĂƂĂ��f�G�ȉ̂ŁA�D�������Ă�B
�r�F�q�ǂ��̓��S�̎��_�Ō������̗̂��s�s�����B�u�ǂ�Ȋ炵�Ă�́v�u���������|�����āv�Ɏ����̂�����肪����B�q�ǂ��̂˂������t�C���^�[�Ɂu�_�C�b�L���C�v�Ɍ���ł���B���̂悤�Ɍ����邩�A����Ƃ��^���Ƃ܂ǂ��Ɍ��Ԃ��B�����͖����ǂ���B�O�߂܂ł̊���̏d�w�ɐ؎���������B
�s�l�F�q���̑f���ȋC���������ɕ\��Ă��܂��ˁB�u���A�邩�ȁ@��傤�����ɂ��������ȁv�����͂�������̓]����Ȃ��ĕ��˔\�Ȃ�ł���ˁB����Ȕ߂������Ƃ͂���܂���B�ł��ςɈÂ��Ȃ炸�ɁA11���ߖڂłe-�em�Ƃ����R�[�h�i�s�Łu������v�Ǝv�킹��Ƃ���ȂǁA�Ȃ��Ȃ��ɂ�����肾�Ǝv���܂��B
�s�x�F�Q�N�O����C�ɂȂ��Ă������v�V����̎��ɁA�����̂����Ă悩�����Ȃ��Ǝv���܂����B��������̂��Ăق����Ǝv���܂��B�I�����i�P�W���߁A�Q�P�A�Q�Q���߁j�����ɂ悭�ł��Ă���Ǝv���܂��B�P�O���߁`�P�R���߂������ł��ˁB���߂Ē����l�̂��Ƃ��l����ƁA���X�ɂ��Ƃ��o�Ă���̂ŁA�_���_���_���̂��ƂP���ߊԂ�u���āA�s�A�m�����̃����f�B��e���A��ċz���Ă�����˔\�ɓ�����@������̂��ȂƎv���܂��B
�g�F�Ȃ������q�ǂ����_�ł��܂�����Ă���̂�����ǁA��l�̗����Ɏx�z����Ă���悤�ʼn����[�܂肪�����B
�e�F�q�ǂ��̗����Ȍ��t�̃e���|�ƋȂ̃C���[�W���҂�����ƍ����A���Ɂu�_���_���_���v�u�L���C�_�L���C�_�v�u�������L���C�v�ȁ@�ǁA�Ƃ��Ă����܂��ł��B�܂��A���ǂ��̎q�����čs���Ă��܂����т����A�Ȃǂ��`����A�ق�ƂɎq�ǂ������ɉ̂��Ă��炦����A�Ȃ�Ďv���܂����B
�Q�U�@���������T�[�N���~���J���ꂿ���ƌĂׂȂ��Ȃ������̓����o�D�U�Q
�h�F�����āA�܂��o�Ă��܂����B��҂̂��ꂳ��ɂ悹��v�������ɂ��݂܂����B�܂��Ⴍ���C����������̕ꂿ���̎p�̕`�ʂ͔��Q�ł��A���������Ƃ��Ă��܂��B�u�������Ȃ��K�v�������Ɍ��ʓI�ł��B�@�������蕷������G��ł��B���̌�̓W�J���������}�Ȉ�ۂ�^���܂��B�u��̂����ɂ���w�v���L�[���[�h�ɂȂ��Ă��܂����A�킩��ɂ����ł��B�l���̋��ƂƂ炦�Ă����̂ł��傤���H
�n�F�W�X�Ƃ����W�J�̋ȂŁA�S�̂Ƃ��Ĉ�������������Ă��邪�A�����Ӗ��ʼn������Z���`�����^���Y��������������B�Ȃ͒Z���̂���Ӗ����^�ł͂��邪�A�������܂��܂Ȏv�����ĂыN�������̂������āA���̂��ߒ��������Ă��܂����̂�����B
�r�F�u�����邢���ƂƂ₳�����������v�Ɓu��������тɂ������ӂ������Ă������߂Ă��ꂽ�v�ł͊i�i�ɈႢ�܂��B��������ƌ��t�Ɖ������݂��؎��ɓ`����Ă��܂����B
�s�l�F�̎��ɏW�����ĕ����܂����B�y�ȂƂ��Ă͊������Ă���Ƃ͎v���܂����A�w�i���ӂ��킩��Ȃ��Ƃ�����Ƃ��ǂ��������c��܂��B�����肪���낢��Ȏ��������Ă�������Ƃ������Ƃ����邩������܂��B�����f�B���f�G�ȁu���̍�̏�ɂ���w�͂܂������Ă��Ȃ��v�������Ȃ��Ƃ��l���Ă��܂��܂��B
�s�x�F�^�C�g������n�܂��āA�̂��i�s�������قǁA�Z�ҏ��߂��Ă�ł���悤�ɁA���ꂱ���i��z�����A�h�L�h�L���Ȃ��璮�����Ă��������܂����B�悭�ł������ɂ҂�����́A�����̂��ł����Ǝv���܂��B�u���������̂�����v��u��̏�̉w�v�Ȃǂ̂��Ƃ��悭�\������Ă��Ď��������ł��ˁB�s�Ԃ�����Ă��܂��B�����܂ł��Ȃ��ł����A�A�����W�����炵���B
�g�F�����Ȃ��Ƃ��v�������ׂ����Ă����D�����́B�S�ɂ��݂��ȁB
�e�F����A���̍�i���܂ߐ~���J�̍�i�̕s�v�c�Ȗ��͂ɒ��ڂ��Ă��܂��B���̒��ł����̋Ȃ̕��`�����_�������ł��B�u���̍�́`�v�f������Ă���悤�ȉf���I��@�A��ۓI�ȃ����f�B���C���B�^�C�g���́u�ꂿ���ƌĂׂȂ��Ȃ����E�E�v���Ƃ̔w�i��͂悭�킩��܂��B�v
�Q�V�@�@�Đ��̑�n�����c���w�Ԃ��Ƃ́��o�D�U�S
�h�F�X�P�[���̂������ȍ����N�Ǎ\���̑S�Ȃ��Ă݂����ł��B���{�R�̕��m�������ŕߗ��ƂȂ�A�w�K����l���Ȍ��ȁA�����̌��t�ŕ\������Ă��܂��B�u�܂ȂԂ��Ƃ͂߂��߂邱�Ƃ��v�Ƃ����̂͌���̋���ɂ��ʂ���^���ł��ˁB�g�Ȃ����яo���ĒP�Ƃɉ̂��Ă����Ȃ��Ǝv���܂��B
�n�F�̌���o���������t�ŒԂ������Ƃ��A���̂܂܁u���v�ƂȂ�����ۂ���B���̂��߁A�Ȃ͂��̃e�L�X�g�����ŒԂ�Ƃ������ƂɓO���Ă���Ƃ�����ۂ���B�O�t��ԑt�A�����Ĕ��t�p�[�g�͌y���ȋ����ɂ��ӂ�Ă��邪�A�e�L�X�g�̐��炩�A�y������������ۂɎc�錋�ʂƂȂ����B
�r�F�悭�����o�Ă��ĂЂт��Ɍ��݂�����܂��B�u�w�Ԃ��Ɓv�̂Ƃ炦�Ȃ����ɔ���������܂����B�^�����Ɛ����͂̂��郁�b�Z�[�W�ł��B
�s�l�F�����Ȏ咣���������̎����A���̉̎����������ȃ����f�B�ɏ���Ē��O�ɓ͂����t�ł����B�䎌�����ʓI�ʼn��y���x���Ă��܂����B
�s�x�F�{���ɂ������ȂƁA���x�����Ȃ����Ȃ��璮�����Ă��������܂����B���̃e�[�}�ō����N�nj������Ƃ������̎��g�݂��̂��̂ɂ��A���^��v���܂��B
�g�F���P�ɖ������N�w�I�Ȑ[�����ɔ�ׂċȂ������������ꂸ��a�����o���Ă��܂��B��т�\������Ă���̂�����ǁA�����Ƒ�l�̊�тł͂Ȃ����낤���B
�e�F�ڂ��������̐�ƊǗ����ɍs���܂������A�e���r�h���}������A�m���ɂ����ł̊w�т͓��{�ł̕ߗ��̈����Ƃ͑S���Ⴄ���̂��Ǝv���܂��B�u�w�Ԃ��Ɓv���l�ԂɂƂ��Ăǂ�ȈӖ�������̂��A���������ƕ`����Ă��āA�����͂�����܂��ˁB
�Q�W�@�t�F�j�b�N�X�\���O�V���K�[�Y�������ւ̌��Ӂ��o�D�U�X
�h�F�s�����ٓP�c�ւ̕s�����Ə�����������邨�������A�����Ȍ��t�łÂ��Ă��܂��B�����A�v���̂������������݂�����ƁA���S�͂��R�����Ȃ�܂��B�X��ʼn̂��Ƃ������ƂȂ�A�_�炩���V���v���ȉ̎��̂ق���������̐S�Ɏc��܂��B
�n�FJAL�̕s�����ٓP���̉́A�Ƃ������Ƃ͂킩�邪�A���̓����̂ǂ����ǂ��\�����邩�Ƃ����_�ŁA���̓��e����ʓI�Ȃ��̂ɂƂǂ܂��Ă����ۂ���B�Ȃɂ������̂Ȃ��Ŏg���Ă���u���v�u��]�v�u�M���v�u�����v�u�ւ荂���v�Ƃ��������t�����܂�ɂ���ʓI������B�w����`���ʼn̂��̂ł���Ȃ�A�悯���ɋ�̓I���e���`��錾�t���K�v�Ǝv����B�Ȃ̓W�J���͎̂��R�����A�e�L�X�g�̐���A������Ƌ����ďI����Ă����ۂ���B
�r�F�u���ԂƋ��͂��ď����������v����������Ɖ̂����Ă����܂����B���̂悤�Ȍ��ӂ̉̂�����Ȃɂ݂��݂������̂���̂Ɋ����������܂����B
�s�l�F�X���Ŏx�����������Ȃ��炤�����Ă���Ƃ����z�����邾���ŋ����M���Ȃ�܂��B�X���Ȃǂł������̂ɂ͉̎����킩��₷���Ĉ�ۓI�ȃ����f�B�����ʓI���Ǝv���܂����A���������Ӗ��ł́u�������̌��Ӂ@�����ւ̌��Ӂv�͉̎����������₷�����ɂ����Ɠ����Ă��܂��B
�s�x�F���̉̂��X���ʼn̂��Ă���p��z�����Ȃ���A�������Ă��������܂����B�����̂��ł����Ǝv���܂��B���x���̂��Ăق����Ǝv���܂��B������ňꌾ�B�O���㔼�Ƃ����Bb���S�Ƀ����f�B�������A�ō���������D�Ȃ̂ł����A���̍\���������ς��āA�����đO���͂����������œ����Ƃ��i���Ƃ��A�����ւƓ����A�͉���Bb�ɂ����������A���̂��Ə㏸�j�A�㔼�ł̍ō����i���Ƃ��Ό��Ӂj��Eb�܂ł�����悤�ɂ���ƁA�����n�����łāA�i����͂������悤�ȋC�����܂����B
�g�F�܂������Ȏv�����`����Ă���B�D�݂�����Ƃ͎v���̂�����ǁu�������̌��Ӂv�ɓ���O�̂Ƃ�����R�ԂƓ����悤�ɂP���ߐL���ĉ̂�グ�Ă͂ǂ����낤���B
�e�F����ǂ����Ƃ����܂������Ȃ������f�B�ɂ̂�A�Ō�́u�������̌��Ӂ`�v�̕����Ƃ̃o�����X���悢�Ǝv���܂��B�����A�u�������̌��Ӂ`�v�̃����f�B�ɂ́A�̂��₷����������ƕ�����Ȃ��Ǝv���܂����B�����ɂ����A�ō��ɋC�����̓��郁���f�B���~�����B�܂��A1�Ԃ̉̎��A3�i�ڂ́u�S���́v�Ƃ������t�Ɂu�`�b�a��`�v�Ƃ��������f�B�ɂ͈�a������܂��A�u�c�b�a��`�v�Ƃ����ق���2�C3�Ԃ��҂�����ƂȂ�Ǝv���܂����A�ǂ��ł��傤�B
�Q�X�@�암�����c���ւ肠�铹���o�D�V�O
�h�F���n��Ɋւ���Ă���̂ōu�]�͂����܂��B
�n�F�u�����ւ̌��Ӂv�Ɣ�ׂ�Ǝ��������Ԃ��̓I�ɂȂ��Ă͂��邪�A�t�ɉ��y���ߑs���ɂ��ӂꂽ���̂ɏI�n���Ă��āA�`����Ă�����̂����Ȃ�ɂȂ��Ă��܂��B���ɓ����̉��t�����Ȃ�e�����̂ŁA���������s���肾�������Ƃ�����A���y�I�ȑi���͂Ɍ�������̂��������B�Ȃ̐��i���w���ł̐�`���ʼn̂��Ƃ������̂ł��Ȃ��A�X�e�[�W�ʼn��t���鍇���ȂƂ��Ă͂�⏬�Ԃ�Ƃ������A�Ȃ̐��i�����s�N���Ȉ�ۂ���B
�r�F�u��ї��Ƃ������ցv�����������̒�����̐��������܂����Ђт��܂��B
�s�l�F��Ԃ̓A���y�W�I�ł������ڂ̃e���|�ł����B���̓e���|��ς�������Ƃ��j�������ŕω����������ł��B���������Ƌ��ɔ���s�i�Ȃ̃e���|��1�Ԃ�3�Ԃ��ς��Ȃ����������̂ł́c�Ǝv���̂ł����B�㔼�̃��W���[�̕����͉��̐������K�v��������܂���B�Z�������̈�ۂ������Ƃ����̂�����܂����A������ƈ�ۂƂ��Ă͔��������ł��B
�s�x�F�����x���̂����̂��ł��܂����B�u���������������āv����̂W���߂����Ɉ�ې[���ł��B��ʂ̐l���̂��ɂ́A���F���͏������������邩�ȂƂ��v���܂��B���ɂ�����肪����ꍇ�͕ʂł����A�����łȂ����F#�͍Ō�̈��i�݂炢��E����F#�Ɂj�����ɂ��āA�r���͑��̉��ɑウ��̂͂������ł��傤���B�܂��AE���ɂȂ��Ă���́u�ւ肠�铹���v�̃����f�B�A�i�|���������܂߁j�͈����Ȃ��ł����A��ԑ�Ȃ��Ƃł�����A�����Ɨǂ����̂͂Ȃ����A�čl�̗]�n�͂��肻���ł��B�������������l���Ă݂܂����B�i����S�j���ꂪ�������ǂ����͕ʂł����A���Q�l�܂łɁB
�g�F�����킢�̐^���������ɂ���J���҂Ɋ��Y�����n�슈���͂������B�ƂĂ��������Ȃ̂�������Ȃ����Ȃ��A�����W��������Əd������
�e�F�i�`�k�̓����ɂƂǂ܂�Ȃ����������̂�����ڎw�������̂��Ǝv���܂��B����ȍL����������܂��B�����A�u�U��|���v�Ƃ������t�͉̂ɂȂ�Ƃ킩��ɂ����ł��ˁB�u�U��i���j�|���v�ƕ������邽�߂ɂ́H�]����̃��Y�����O���ƕς��Ȃ��̂ł����A�����H�v������Ƃ�����������܂���B���Ƃ́A����̍H�v�A�S�̂̐��������āA�̂��₷���o���₷���̂ɂ��Ăق����Ǝv�܂����B
�R�O�@���̂����������c������������������܂������悤�Ɂ��o�D�P�Q
�h�F�@A�̕����̉̎����ƂĂ��������ł��A����ɑ��������̉����̔�Q�̗L�l���W�X�ƌ���Ă��āA�ނ��닰�|�����������܂��B�����ւ̊�]�������ł͂Ȃ��̂ł��������͂�����܂��B�悭�܂Ƃ܂Ƃ܂�����i�ł��B
�n�F�����̂��̂͂ƂĂ����R�ŁA�^�C�g���ɍ��߂�ꂽ�肢���\���邱�ƂȂ��`����Ă�����̂�����B�Ȃ����̃����h�`���ɂȂ��Ă��āA�����h���ɑ�������A�̐��������邭�����₩�ȋ����ōD�������Ă�B�}�����ɑ�������B�AE�AG�̐��������p�^�[�������Ă���̂��C�ɂȂ邵�A�R�[�_�ɑ�������H�ł̃n�[���j�[����͂�ތ^�I�ł���̂��ɂ��܂��B�S�̂Ƃ��Ă͏d���e�[�}�ɂ�������炸�A�l�Ԃ̉c�݂̉��������`����Ă���̂ɂȂ��Ă���B
�r�F�G�l���M�[�̂��鉉�t�Łu���ǂ������݂̂炢���悲���Ă͂����Ȃ��v�̑i���Ɓu�g���{�E���ȂفE���Ȃ䂫�v�Ȃǂ̏�i���悭���Ȃ�Ă��܂����B
�s�l�F�R��I�Ȃӂ邳�Ƃ̕��i�ƌ����̕��i�����������ۓI�ȋȂł��B�`���t�ƉĂ̕��i�ɂ��ꂼ��8���߂����ĂĂ��܂����A�㔼�̏H�Ɠ~�̕��i�ɂ�4���߂��ƂȂ��Ă��܂��B�K�����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł͂���܂��A�Ȃ̍\�����킩��₷���Ƃ������Ƃł́i�A���o�C�I�Ɍ��t�𑝂₷�Ƃ�����Ƃł͂Ȃ��j�����𑵂���Ƃ�����Ƃ������Ă��悩���������m��܂���ˁB
�s�x�F�̂��p���ōs�������ǂ��̂ł��B���Ȃ�̎��Ԃ������č��ꂽ�Ǝv���܂��B�̎��ƃ����f�B�̊W�A�a���̗���A���t�ȂǁA���ׂĐ������Ă��܂��B�o�����̃����f�B�ƂT�P���߁`�T�S���߂����ɂ͓��Ɉ�ۓI�ł����B�����AB�̕����́AA�Ƃ͈Ⴄ����Y���̂ق����ǂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���H���͈Ⴄ�Ƃ͂����A�����x���Ŏn�܂邱�̌`���A�R�X���߂܂łɑ����ĂP�W��o�Ă���̂͂������ł��傤���HE��G�̕����ŏ��߂Č���鉹�f�ނ��g���āA�S�̂̍\�����l������@�����邩�Ǝv���܂��B�i����T�j
�g�F�Ⴂ�l���������̖��ɐ^���Ɏ��g��ł���p�ɗ���������������B����A�����Ȋp�x����V���ȍ�i�����ݏo����邱�Ƃ����҂������B
�e�F��������̋Ȃ͂����ƂĂ�����グ��ꂽ������������܂��B���̋Ȃ̃��`�[�t���G�߂̎��R�̕`�ʂ������������f�B�ʼn̂��܂��B����ŁA�������`�[�t�ɂ���āA�D��ꂽ���R�▲�E��]�Ȃǂɑ���߂��݂�Â��ȓ{�肪�̂��Ă��čI�݂ɍ\������Ă��܂��B�h���������������ꍇ�A�Ƃ�����Ƃ���͉̂ɂ��Ȃ��ŁA�ƌ��������Ȃ邱�Ƃ�����܂����A���̍�i�̏ꍇ�A�\����}���ĐÂ��Ɍ���Ă��܂��̂ŁA�����͂�����܂��B���ꂾ���ɁA�Ō���f�̕����ւ̊��҂����܂�܂����A����܂ł̗����悤�ȃ����f�B�Ƃ͂������C���p�N�g�̂�����́i���܂̍�i����������������Ƃ��ӎ����ď�����Ă��邱�Ƃ͂悭�킩��܂����E�E�E�j�����������ƁA�~�����Ďv���܂����B�ł��A�ƂĂ��͍삾�Ǝv���܂��B
�R�P�@�����Ƃ肨���������t���o�D�R�R
�h�F�V���v���ł��������x�̍����̎��ł��ˁB�l�m�ꂸ�����A�t��҂Ԃ����ɁA�������̎p�������˂Đ������Ă��܂��B�u�t�̊����v�Ƃ��������錾�t���������߂Ă��܂��B���̍�i�́u�K���t�͂���v�Ƃ����悤�Ȓ��B�ȕ\�������Ȃ��Ƃ��낪�����ł��B�������炸�ɁA������̃C�}�W�l�[�V���������N����\���͑�ł��B
�n�F8����12���q�̃��Y���ō�Ȃ��Ă��邪�A���̃��Y���Ǝ��̌��t�������Y���Ƃ��K��������v���Ă��Ȃ��悤�Ɏv����B�u�i�R�́j���݂��v�u�i�����j���낵�v�u�i�t�́j���ނ��v�u�i�[���j�˂��́i��j�v�Ƃ��������t�̕����ɕt����ꂽ���Y���ɂ���a�����o����B
�r�F�����Ƃ����������A�܂��Ɂu�������t�v�ւƋ��ӂ���ދȂƉ��t�ł����B
�s�l�F��Ȏ҂Ȃ̂ł����A�ꌾ�R�����g���B�����̍u�K��ŁA�Љ�ɑ����Ƃ��Ƃ��Ă�����������̑��q����ɑ���v���Ȃǂ����̏�ł��������āA���̔ނɃG�[���𑗂낤�Ǝv���Ȃ�t���܂����B���t���f�G�ł����B���N��ɂ�������đf�G�ȃA���T���u���ŕ��������Ƃ͍���Ƃ��Ă͖{���ɂ��ꂵ���ł��B
�s�x�F�Ȃ��Ȃ��̖��Ȃł��B�����~���߂����A�k���ɏZ�ނ��̂ɂ��������Ȃ����E�̂悤�ȋC�����܂��B�t�̃G�l���M�[�������܂��B�ގ��i���Ȃ��V�N��������܂��B��̓I�ɂ́ABb�̃R�[�h�̎g�������ʔ����ł��ˁB
�g�F�������ɒ��ڂ���Ǝ�̂���F�����⎩�R�̉����v�������ׂ�̂����A�Ȃ́A�a���]������ۂɎc���ă����f�B�[�Ǝ������܂蕷�����Ă��Ȃ��B
�e�F�z�Ƃ����Ԃ̎p�Ɏv�����d�ˁA�w�̐L�т��i�������̂ɂȂ��Ă��܂��B�u���m�ԂЂƂ�v�܂ł̂�����Ƃ��������������ł��ˁB���́u�`�ς��Ȃ���v�܂ł��čŌ�ɂ������u�[�������������̉��v�������܂ł��\����Ă��Ȃ��C�����܂��B�u�[������v�����������\���̂�ꂽ�̂��Ɂu��������̉��v�Ƃ����������A�Ɨ����Ĉ�ۓI�ɉ̂���A�Ƃ����悤�Ȍ`�ŁE�E�E�ȂǂƎv�����肵�܂����B
�R�Q�@D�T�P�����c���N�̐S�Ƌ��Ɂ��o�D�P�W
�h�F��ɐ������F�ւ̎v������������Ɠ`���܂��B�u���g�����Ղ�̏Ί�v�ɏے������F�̎p���֊s���͂����肵�Ă��܂��B�ǂ��̂ł��B
�n�F�Ǔ��̂Ƃ��Ă̐��i���炩�A�u�����`�v����̕����������Ɛ����̉��悪�����͈͂œW�J����Ă���A���n���Ȉ�ۂ���B�u�S�ė����ꂽ�X�Ł`�v����̓W�J�́A���y�I�ɂ͂ƂĂ��[�����������ł͂��邪�A��������ʓI�ȕ\���ŏ��X������Ȃ��B�����̂����������t���f���炵�������B
�r�F�j�������̂����狭���B�u���݁v���v���S�����������ɓ`�����Ă��܂����B�V���́u���݁v�ɂނ����ĉ̂��Ă���悤�ɁA�S�h���Ԃ��܂����B�J������̈�[����ʂƂ��đ}������Ă����������B
�s�l�F�v���������ς��l�܂����̂ł��ˁB�����c���̐l�����Â�܂��B�u�D�̒������]���@�����Ԃ��ꂽ���t���@�Y��Ă����̂��@�E���W�ߒT���n�߂�����Ȃ̂Ɂv�Ƃ������t�����ɔ���܂��B�l�I��͈̔͂̂��ƂɂȂ��ċ��k�ł����A�Ȓ��ɂ��������D�L�����ق��������Ȃ��Ǝv���܂��B
�s�x�F�c������̒Ǔ��ɂӂ��킵���A�����̂��ł����Ǝv���܂��B���̉̂Ƌ��ɁA�F����̐S�̒��ɍ�������͐��������邾�낤�Ǝv���܂��B�����Ɗ��ł����邱�Ƃł��傤�B
�g�F�M���v�����`��������
�e�F�̂����Q�ɂ��܂����X����́u���X�ؐ߁v�S�J�̏�L���ȉ̂ł����B�S���Ȃ������Ԃւ����錾�t����ϋ�̓I�Őh�������ӂ����e���悭�`���Ă���Ǝv���܂��B�ł�����A�������������ȕ��͋C�ŁE�E�E�ȂǂƊ��҂����܂�܂��B
�R�R�@���Ƃ��܂��恃�����Ƃ܂��Ă����恄�o�D�P�T
�h�F�V�������ɑ���v�����S�҂�ʂ��ĂقƂ����Ă��܂��B���̎v���̓^�C�g���ɏے�����Ă��܂��B������̐����^�̂Ɗ����͕�������������Ȃ���̂ł��ˁB
�n�F���쎍���̂��Ƃ����_�ŁA�����̂����������t�B�Ȃ����R�ȓW�J�Ŏ����ɂ��ӂꂽ�����ƂȂ��Ă���A�悭�܂Ƃ܂��Ă���B�����Ȃ�ƁA���̎��̂����ЂƂ��ݍ��v���Ƃ������̂�����̂��Ă��Ă��ǂ��̂ł͂Ȃ����Ƃ����v���ɕ�܂��B
�r�F����Ƃ������݂����ӂ��̂ł��B�a���ւ̂�낱�т��Ђ낪��܂��B�������e�[�}�ɂ҂�����ł��B
�s�l�F�����O�Ɂu���v�Ƃ������̂����s��܂������A���̃e�[�}�͑������l�ɂƂ��Ă͕��ՂȂ��̂Ȃ̂ł��傤�ˁB�u�Ђт��n��`�v�͐S�Ɏc��ƂĂ���ۓI�ȃ����f�B�ł��B
�s�x�F�����̂ł��ˁB����ɉ��t�����炵���ł��B���ɂȂ����������̂��Ƃ��v���o���Ȃ���A�������Ă��������܂����B
�g�F���̒��g���犴����̂͂ق̂ڂ̂Ƃ��炩���g�������������B�������Ȃ͓x�X�h���}�`�b�N�ɕ\������߂��Ă��̏_�炩�����`����Ă��Ȃ��B����グ�悤�Ƃ���قǂɓ����悤�ȎR���x�X����A���ꂪ�ӂɔ����Ĉ�ۂ𔖂ꂳ���Ă��܂��̂ł͂Ȃ����낤���B
�e�F���̂��̊�сA���̂��̗͋����A���̂��̂������Ƃ������v���C���������炩�Ɏv�������Ղ�ɑn���̂��Ă��Ċ����ł��B3�̕�������ł��Ă��܂����A�ŏ��̃��`�[�t�����R�Ŕ������̂ŁA2�ڂ̃��`�[�t���g�킸�A�ŏ��̃����f�B���J��Ԃ��`�ł��̎��ɂ��āA��������u�����n��`�v�ƍł������I�ȕ����ւƓ����Ă�������A�S�̂��V���v���ɂȂ�Ō�̕��������Ȃ萶���Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���܂����B���Ƃ�����̃\�����f���炵���A�ƂĂ������I�ȓ��e�ȂŁA�݂�Ȃ��̂���悤�ȕ��Ր�������܂�����A����ȃ\���O�ɂȂ�A�Ǝv���܂����B
�R�S�@�����₷�q���������o�D�Q�U
�h�F��҂Ɖ̂̏o������������߂ď��������Ă��܂��B���ۓI�A�ތ^�I�ȕ\�����C�ɂȂ�܂��B
�n�F�̂ɂ�鎩���j�Ƃ�����ہB�����j���瓥�ݏo���A�L����肩���₢������Ƃ����u�\���v�ɂ��Ă������߂ɁA�����Ǝ��̍\��������K�v������悤�Ɏv����B�Ȃ͂����������̐��i�������āA�e�L�X�g�������ɉ̂ɂ��Ă͂��邪�A��͂薢�����̕����f���āA��������₭�ǂ��Ȃ��Ă���ӏ����U�������B
�r�F�̏��͂Ɖ̂̕\��䂽���Ɂu�����Ђ�����Ɂv���ɂЂт��܂����B
�s�l�F���������������ĉ̂��Ă����邱�Ƃւ̊��ӂ̂����ł��傤���B���������f�B�ɏ���Đg�̂̒��ɂ��݂킽���Ă��銴���ł��B
�s�x�F�]�k�ł����A�ǂ����ċ{��i���k�j�̉̂���̕��X�́A����Ȃɉ̂����܂��̂ł��傤���H���X��������Ƃ�������A�����ĕ���������B���́u�����v�������̂ł��ˁB�u�킽���v�̎v����Ԃ�ꂽ�����A�ƂĂ��ǂ��ł��Ă���Ǝv���܂����B
�g�F�Ȃ̐���オ�肪�����đS�̂���╽�Ɋ����Ă��܂��B������Ԃɓ���O�̉䖝�����ɂȂ�̂ł͂Ȃ����낤���B
�e�F�J���c�H�[�l���~���[�W�J���i���o�[�̂悤�ȋȁB�����̐l���Ɖ̂ւ̎v�����I�݂ȍ�Ȃɂ̂��č��炩�ɉ̂��グ�Ă��܂����B�̂̂��܂���҂ɂ҂�����̍�i�ł��B
�R�T�@��䍇���c�ᐯZ�����l��͂������o�D�Q�O
�h�F���݂������̂��ӂ��̎��ł��B�u�����͂��ɂ��Ƃ߂Ȃ��E�E�E�E�ڂ���������߂���v�I���W�i���e�B�[���ӂ��̎��Ɉ������܂�܂��B
�n�F�Ȃ̂��肪�ƂĂ������B�|�b�v�X�̒�^�p�^�[����ł͂��邪�A�T�r�̕���������ɗ�����Ȃ��œƎ��̖����o���Ă���Ƃ��낪�����B�����Ȃ�ƁA���̓W�J�����V���v���ŁA���e��������ʓI�ȕ\���ɂƂǂ܂��Ă���Ƃ��낪�ɂ����B
�r�F�����n���̂���A���t�̂͂����肵���̏��B�y����ʼn̂��Ă���B��҂̃G�l���M�[�Ɉ��|����܂��B
�s�l�F���̒��z�������ł��ˁB�g��ꂽ���t���ƂĂ����͓I�B�u�l��̌����͏\���b�Ł@�ڂ���������߂���v�u�܂�����̈������X�ɐ��܂�@���͂��߂Ă�������̂�����v�Ȃ�ĐV�N�Ŗ������ɖ����Ă���̂��낤�B���т���̑f�G�ȋȂɉ����A�݂Ȃ���̐V�N�ȉ��t���f�G�ł����B
�s�x�F�u�₩�Ő������������ǂ��̂��ł��܂����ˁB���́A�R����S�̕�������Ԃ̂��C�ɓ���ł��B���t�����Ă��ł������A��ԑ�ȉ̎����������Ȃ��A���̐����ɏ�����Ă��܂��ӏ�������܂����B
�g�F�G�l���M�b�V���łƂĂ�����₩�Ȉ�ہB�Ƃ��Ɂu�ڂ��͂������̂ڂ��ł͂Ȃ��v�Ƃ����Ƃ��낪�������y���V�N�ōD�������Ă�B
�e�F���̏W�c�̎��������\���ɐ����������ƋȂŁA���̂��V�N�ȃG�l���M�[�𐐁X������ȂɎd�グ�Ă��܂����B���t���Ȃ��Ȃ��̂��̂ŁA�S���ɍL����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�R�U�@�ǂ炲���T�[�N�������̒��Ł��o�D�Q�W
�h�F�R�����̕������肤���ӂƊ�]�����߂����b�Z�[�W�\���O�ł��B�u���̒��Łv�u�����Ă䂭�v�u���������ǁv���x�����t���C������ăe�[�}��[�߂Ă����܂��B���̉̂ɂ��߂���҂̈Ӑ}�͏[���ɂ����܂��B����ЊQ�������e�[�}�Ƃ����Ȃ������A���̒��œ��k�̎��R��\������̂Ɂu�Ђ���c��ځv�u����̂Ȃ���v�̂悤�ȗތ^�I�ȕ\�����悭�����܂����A������H�v�~�����ȂƎv���܂��B
�n�F�������ƂĂ��̂т₩�ȓW�J�Őe���݂₷�����̂����邪�A�T�r�ɑ�������u���̒��Ł`�v����̐�������₭�ǂ��Ȃ��Ă���̂��ɂ����B����͎�������܂ł̂��Ȃ��̓I�Ɂu�R�����v��`������������A������`�Łu���̒��Ł^�����Ă䂭�v�Ƃ����t���[�Y�Ɍ��т��Ă��邽�߂Ǝv����B�Ôg�ɏP��ꂽ���̍Đ����肤�C����������ɐ����͂�����̂ɂ��邽�߂ɁA�����ЂƍH�v�K�v�Ǝv����B
�r�F����̂���̏��ƋȂ̗͂����C�������Ă���܂��B4�s�`�U�s�̐߂̂��鎍�ɂ��Ă��悢�̂ł́A�Ƃ̍��͂������܂����B
�s�l�F�n���̊F���n�肤�������Ƃ�����Ȃɂ��G�l���M�[�Ɛ����͂�����i�ɂȂ�̂��Ȃ��Ƃ��炽�߂Ċ������Ă��܂��B�����悭�ᖡ���ꂽ�̂ł��傤�ˁB�u�������܂��Δg�̉�����������v�Ȃǂ͊F����̌��ӂ����������܂��B�����ҋȂ��悭�����Ă���Ǝv���܂��B�������̃A�J�y���������҂������ƈ����悹�܂��B�������܂����B
�s�x�F���߂Ē������Ă������������ł̂��������̉�̎�����A�ЂƂ����ې[���̂ł����B�u���̒��Łv�̕����i���Ƃ��Q�V���߁A�R�P���߁A�U�W���߂Ȃǁj�͎l���ɂ����Ƀ��j�]���ł����̂��Ƃ��v���܂����B�ԑt�����̉���������Ă��ł��ˁB�Ō�̃��j�]�������ʓI�ł��B���Љ̂������Ă��������B
�g�F�̋��ւ̌����v�����u���̒��Ő����Ă���@���̒��Ő����Ă䂭�v�̌J��Ԃ��ŋ����v���Ƃ��ē`����Ă���B
�e�F�ڂ��̒m���Ă���o�C�I���j�X�g���R�����ƂȂ���x���R���T�[�g�Ȃǂ����Ă��܂��B���������A�݂�Ȃł��������̍�肪����Ă��邱�Ƃɂ܂���ϊ������܂��B���̂����ɁA�̂��ƂĂ������ł��B�u���̒��Ő����Ă����v�̂������Ƃ������͓I�ȃ��`�[�t���f�G�ŁA���������ɑS�̂��悭�܂Ƃ܂��Ă��ĉ̂��₷���̂Ɏd�オ���Ă��܂��ˁB�����ҋȂ̊y���́A�A�Q�S�`�Q�U���߂̓R�[�h���炷��Ɖ��삵���ق����ǂ��Ǝv���܂��B�܂��A�U�Q���߂���̔��W�A�]�����Ȃ��Ȃ������ł����A�U�T���߂̃R�[�h��A7sus4�łȂ��AAm ��F�ł��傤�B�܂��A�W�R���ߖڂ���̃o�X�̒����L�����͂����Ƃe���悢�Ǝv���܂��B�ׂ������Ƃ������܂������A�Ƃ��Ă��f�G�ȋȂł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ł��B
�R�V�@�������ӂ���܁������̂Ђ��炵���o�D�P�U
�h�F��u�Ŕ����̗[���ɕ������A��čs���Ă����A�G��ȉ̎��ł��B�Ђ��炵�̐��͐Ȃ��������悢�܂��B�J�i�J�i�E�E�E�Ƃ����Ђ��炵�̐��������f�B�[�ŕ\������̂��A�̂��̂�����ȂƎv���܂����B
�n�F�u�J�i�J�i�J�i�J�i�`�v�̂Ƃ��낪�ʔ����B�Ȏ��̂͂����̃V���v�������O�ꂵ�Ă��āA���̂��߂ɁA���́u�J�i�J�i�`�v�����ʂ����Ă��邪�A���̓��e�͂����Ɠ��ݍ��\�����~�����B
�r�F�J�i�J�i�̋������������ɂ��肩������܂��B���̂��Ƃ��Đ����邱�Ƃւ̎����݂��S���k���Ă���܂��B��i�������Ԑ��E�ł��ˁB
�s�l�F�����̍u�K��Ő��܂ꂽ�������A�����荞�܂�ăI���R���Ɏ������܂�܂����B����̃I���R���̓����ł��ˁB���̉̂����т���̃A�����W�Ői�����Ă̓o��ł��ˁB�߂����ȋȒ����Ђ��炵�̖����ƂȂ��ċ����܂����B
�s�x�F���̎��͂������ł��ˁB���̎��ɂӂ��킵�������f�B�����܂����B�J�i�J�i�̕��������ɏG��ň�ۓI�ł��B
�g�F�S�̔߂������Ȃ��`����Ă���R��ɂ��ӂꂽ�ȁB�u�J�i�J�i�d�v��������ƒ����Ă��ǂ������Ă��܂����B
�e�F�����n��u�K��ō��X�؏i�q����̈�ۓI�Ȏ��ɁA�f��̃e�[�}�\���O�̂悤�ȍ��X�ؐL���̏���I�ȃ����f�B�����A�����Ĕ��\����܂����B��Ԃ̕������ǂ���͂�͂�u�J�i�J�i�E�E�v�ł����A���̑O�̕�������̉�����Ƃ��������ŁA�����ЂƂ������A�O�b�ƐS�����ނȂɂ�����������ō��ł��ˁB
�R�W�@����̂����������ٗp�u���[�X���o�D�V�Q
�h�F����̃I���R���B��̎�N�J���҂��e�[�}�ɂ����Ȃł����B�Ⴂ�l���̂��Ă����̂ł��؎������`���܂����B�O���̌ٗp���߂��錵��������A��]���āu�㔼�̑��v�E�E�E�P�������Љ�����낤��A�v�Ƃ�������˂ł��B�܂��܂���������A����O�i���Ă��O�����炢��ނ��Ȃ�������Ȃ�����ł��B�O���̉̎��ɐS�Ă����l�������Ă��܂������B���ꂢ�Ȍ��_���������ď����K�v�͂Ȃ��ł��B
�n�F�O���̃\�������A�����Ȃ��ƂĂ��ǂ��B���Ɏ��̓��e���i�̂��ȂƂ��Ă����������������K�v������Ǝv�����|�Ⴆ�u�ۊO������������Ă����v�́u���v�����A7�|7�̃��Y���ɂ��낦��Ƃ��j�ƂĂ������ŁA����ƎЉ���悭�f���o�������e�ɂȂ��Ă���B�Ƃ��낪�����̕����ɂȂ�ƁA�Ƃ���Ɋy�V�I�ȋ����ŁA�u���v�A���Ȃ��͂�邭�Ȃ��v�ƁA�����̂Ȃ��m��t���[�Y�ɂȂ��Ă��܂��B����ł͂������������f�����O�������̃X�g���[�g�ȑi������܂��Ă��܂��B���̓_���傫�Ȗ��_�B
�r�F�u�������傤�ԁA���Ȃ��͂�邭�Ȃ��v�����ҐӔC�A���Ȕے芴�ɏP�����҂ւ̗�܂��ɖ����Ă��܂��B�Ⴂ�l���̂������Ґ�������h���Ԃ�܂��B
�s�l�F�\���̂���l�̉̂͐S�ɋ����܂����B�����ŋ��k�ł����A���t���q�Ɩ����Љ�ɑ���o�������e�Ƃ��ẮA�h���ꂵ���A������������l�����̉̂Ƀ_�u��܂��B��Ԃ̉̎��̂悤�Ȃ��Ƃ����N�����Ă��Ȃ����ƋC�ɂ��Ȃ�܂��B�u���[�X�Ƃ��Ă��邩�炩�ǂ����͂킩��܂��A3�i�ڂ́u�s�̗p�ʒm�`�v�̂�����̃R�[�h���a��|�`�ƂȂ��Ă��܂����A�f���ɂf�|�`7�ł悩�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�㔼�����͍u�]�ψ���ł����낢��ƈӌ����o����܂����B8���߂Łu�����₯��Љ����낤��v�܂Ŏ����Ă����̂͂�����Ɩ��������邩������܂���ˁB�ꍇ�ɂ���Ă͑O���̕����ɏd����u���Ď�҂����̏�`����Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ����ł������̂�������܂���B����Ɋ��҂��܂��B
�s�x�F�g�߂ȃe�[�}�������̂ɂȂ�܂����B����l�̃\�������炵�������ł��B�u�s�̗p�ʒm�v��Bb�̃R�[�h�����܂��ł��B���v����̌㔼�ł����A���߂Ē������Ƃ��́A�ł��Ђ�����Ă����҂̐��E����u�P����Љ�v�܂ł��������}�����銴�����܂������A���^�����J��Ԃ������A����ł������̂��ȂƎv���n�߂Ă��܂��B
�g�F�g�ɂ܂���錻�����悭��������ɂ��Ă���B�㔼�̍�������ˑR�y�V�I�ɂȂ��āA��������Ƃ�������邪�A�E�C�Â������v�������ӂ�Ă��āA����ŗǂ��悤�ɂ��v���B�U���ߖڏI���u����Ǝꂽ�ʐڂ����w��x�v�̘a��(D�V)�͂���a����������B
�e�F���܁A���߂��Ă���̂ɒ���ł����B�ڂ����u���b�N��Ƃ̂��ƁA�Ȃ�Ƃ����ĉ̂�����̂��A�Ǝv���Ă��܂��B�O����������������݂肳���Ȃ��`�ɂ��Ă����ł������A���Ȍ�����\�����Ăق����Ǝv���܂��B�u�������傤�ԁ`�v�����́A��l������S�����邱�Ƃ�������̂ł͂Ȃ��A�������������ɗ�����������҂̃��b�Z�[�W����ꂽ��ǂ��ł��傤���B�������A���҂��Ă��܂��B
���̂����Ƃ����ł��Ȃ����o�D�V�R
�h�F�l�̎��ɍۂ����A�Ⴂ��҂̐^���ȋC�������S�҂���`���܂��B�u���Ȃ��v���ǂ�Ȑl�������̂��A���C�Ȏ��̗l�q�������ė~�����ł��B���Ȃ��̎p���`���A���������߂��݂����L�ł��܂��B
�n�F�ʗ��̉̂Ƃ��āA���͂ƂĂ��悭�܂Ƃ܂��Ă��āA�����̂��������������s�Ԃ��犴������B�Ȃ�8����12���q�ō�Ȃ��Ă��邪�A���̃��Y�����S�̂Ƃ��Ă�₭�ǂ���ۂ������炵�Ă���B�����ăt���[�Y�`���̉�������̕������Ȃ�L���i6�x�A5�x���j�A�����f�B���C�������M�N�V���N������ۂƂȂ��Ă���B���ꂪ�ɂ����B
�r�F�V��̂��̂��A�Ŋ��ɂނ����Â���l�ւ́u�����Ɖ������Ă��������v�̐^��܂������ɓ͂��Ă��܂��B�������ۂ��Ȃ������オ���Ă���Ƃ���ɍD���B����̐l�̓����i�J���j���`�ʂ����Ƃ����ł��ˁB
�s�l�F�₳�������₳���������f�B�̒�����������Â̌���̗l�q�����������܂��ˁB�u���������Ƃ����ł��Ȃ��v�Ȃ�Ă������Ƃ͂Ȃ������͂��B���b��������A��������������A���ɂ��Ă�����Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��������͂��B�����Ă���ȑf�G�Ȃ������ł������Ƃ��ւ�Ɏv���܂��傤�B
�s�x�F����̍������Ȃ��Ǝv���܂��B���͂��̉̑�D���ł��B���Ɂu���Ȃ�����炤�������ꂾ���Łv�̕����̐F�����A�����ĂȂ�ƌ����Ă��A�u�Ȃɂ��A�Ȃɂ��Ȃɂ��ł��Ȃ��`�v�̕������ō��ł��B�����A�u�����Ɓv���A�u�����Ɓv�ɕ������Ă��܂��̂ŁA�i������J���Ă��܂����j�u���v���ǂ��������邩���ۑ肩������܂���B�u�b�������������v�Ɂu���v�͔��ɂ��܂��ł��B
�g�F�ƂĂ��D�����ɂ��ӂꂽ���B�ҋȂ��f���炵���B�����f�B�[�ɂ��Ə�������オ�肪�~�����B
�e�F�������̌���ł̎v���A�S���Ȃ낤�Ƃ��Ă���l�֊�D�����A�h������������`����Ă��܂��B�ȂƂ��Ă��悭�ł��Ă��āA���݂��݂Ɗ����������Ē������܂��B�u�̂����Ƃ����ł��Ȃ��v�Ƃ����^�C�g���ŁA�܂��ɂ����v���ď����Ă�����̂ł����A�z������ꂽ���̕��́A����Ȃӂ��Ɏv���Ă��炦�đ�ύK���ł��ˁB�Ō�́u�̂����Ƃ����ł��Ȃ��v�Ɣے�`�ŏI���Ȃ��ق��������ł��傤�B
�R�X�@�����W�c���̂�тƂ܂ꁃ�t�N�V�}�ւ̎v�����o�D�S�T
�h�F��������Ƃɍ쎌��������i�B�Ԃɑ������̋��ւ̎v�����`����Ă��܂��A�S�ɓ͂��G��ł��B�Ԃɂ�������ď������̂͐����ł��B�\��������̂������Ƌ��S�͂��ɂȂ�܂��B�����P�O�����ɕ����A�쑊�n�A�ъّ��A�Q�]����K�₵�܂������A���̉̎��̂Ƃ���ł����B�c��ڂɂ̓Z�C�^�J�A���_�`�\�E���炫����A���ɏオ�����D���܂�ʼn��F���C�ɕ�����ł���悤�ł����B
�n�F�Ȃ̓W�J�����ŁA�����ƋN���̂�������W�J�ɂ��Ă����K�v������Ǝv����B�^�C�g���ŕ\���������e���A�����Ɨ����ȉ̂��葤�̎v���Ƃ��Ď����Ȃ��\�����Ă����K�v������̂ł́H
�r�F�X�~���̂͂ȁA�͂邵����̂͂Ȃɑ������t�N�V�}�ւ̈���`���Ă���܂��B���l���ł����A�ڂ����Ƒ傫�ȃX�P�[���ɋz�����܂�܂��B�u�t�N�V�}�v�ƕЉ����ɂ����薼�ɂ��Ӗ�������ɈႢ����܂���B
�s�l�F�Ԃɑ����āA�X�ƒW�X�ƃt�N�V�}�̏t���������B�S�ɋ����܂��ˁB�Ō�́u���Ă���@�l�����@���̃t�N�V�}�@�v���v�ɂ�����ƃh�L�b�Ƃ���̂́A�[�ǂ݂������ł��傤���B
�s�x�F���̉̂̃e�[�}�⎍�ɂ͐[���]�C�������āA�ƂĂ��ǂ��̂ł����A�܂��Ȃ��i���t���j�n�����Ă��Ȃ������ŁA���X�c�O�ł����B���Ƃ��u�Z�C�^�J�A���_�`�\�E�v���̂ɂ���̂͂ƂĂ�����ł��B�i�t�ɍl����ƁA���܂��̂ɂȂ�Ζʔ����j��������̂ł��ˁB�S�̂̍\����������x�ᖡ���A�Ȃ���蒼���ƁA�����Ƃ����̂ɂȂ肻���ł��B
�g�F���ɂ��߂�ꂽ�v�������ӂ�Ă���B�����A�t���[�Y���킩��ɂ����B�ȁE�����ɂ��������Z���P�ԁE�Q���d�Ɛ������Ă͂ǂ����낤���B
�e�F�����n��u�K��炢���Ȃ����̂����܂�Ă��܂����B�l�̂��Ȃ��Ȃ����n�ɃZ�C�^�J�A���_�`�\�E������A����ȕ����Ɏv�����͂��ĉ̂��邱�̉̂̓��e�ƋȂ��҂�����ƍ����Ă��āA���̂܂ܑf���ɐS�ɂ������Ɠ����Ă��܂��B
�S�O�@�ƊC�̍����c�����̑��������o�D�X�O
�h�F�u�V�x���v�ɑ傫�ȃG�[����������̂ł��A�e�[�}�������ł��B�����ȉf��ق����̐l�X�Ɉ�����A�ւ�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��`���܂��B�^�C�g���������ł��A��肢�B�������A�܂��߂ɐV�x���̗��j����邾���ł͏������̑���܂���ˁA��f���ꂽ�f��̘b�Ȃǂ������Ăق����ł��A�f��u�j���[�V�l�}�p���_�C�X�v�ɕY���悤�ȕ��͋C��������ꂽ��ō��ł��B
�n�F���t���C���Ɂu���̑������݂čs�������v�Ƃ��邪�A�ł͂��́u���v�Ƃ͉����A�����̋Ȃ̂Ȃ��ŋ�̓I�Ɍ���Ă�����A�̂Ƃ��Ă����ƃ��A���ɔ����Ă���Ǝv���B�����̂��̂���͂育����ʓI�ȕ\�w������Ă��邾���Ȃ̂ŁA�Ȃ����̃R�g�o�ɉ���t���������A�Ƃ�����ۂł���̂��c�O�B
�r�F�������p��Ă����A���������̂Ȃ��V�x���B�����Ƃ����O�����Ȑl�Ƃ̂Ȃ��肪�y��ƂȂ��Đ��܂ꂽ�����̂��������n��ł��B�˂����̂���Ƃ���ɕ���������A�^���̂���Ƃ���ɉ̂����܂��B
�s�l�F����ȉ̂����{���ɂ�������ł���Ƃ����ƕ�����g�߂Ɋ�������̂�������܂���ˁB�u�ŋ���������`�v�Ɓu�ɐ��̏����ȁ`�v�Ɓu�c��̎v�����`�v�����������f�B�œ����̂͏����P���Ȋ��������܂��B�u�ɐ��̏����ȁ`�v�͕ʂ̃����f�B�œ����Ă͂ǂ��ł��傤�B�M�^�[�R�[�h�ƃn�[���j�[�̃`�F�b�N���B
�s�x�F���̉̂̂悤�ɁA�e�[�}��ړI���͂����肵�Ă���̂͂������Ƃł��ˁB�x�z�l�����ꂽ���Ƃł��傤�B�Ō�́u���̂Â����v�́A��x�����ł͂Ȃ��A�Q��A�R��ƌJ��Ԃ������C�����܂����B����U�@�����܂Łu���Ƃ��v�ł����B
�g�F�n��̕������x���Ă����Â�����Ɋ鈤��������B��x�K��Ă݂����Ȃ�B�Ȃ̂܂Ƃ܂�ƌ����_�ŏI���̂S���߁u������������͂��܂��v�̃t���[�Y���J��Ԃ��ĉ̂��Ă݂Ă͂ǂ����낤���B
�e�F���̏����ȉf��فu�V�x���v�̉����̂́A���{���̂��������f��ّS�̂ւ̉����̂ł�����܂�����A�܂����̉̂�����ꂽ���Ƃɑ傫�ȃG�[����������܂��B����̃R�����g���Ƃ��Ă������ł��ˁB�Ȃ́A�܂��A�u�ɐ��́`�v���u��葱���`�v�Ɠ����o�����̃����f�B�ɂ�����A�u�h���푈�`�v�̂Ƃ���́A����������������x�J��Ԃ��`�ɂ��āA���̑O�̕����Ƃ̃o�����X���悭�����ق������������Ǝv���܂��B�f��ق̂ЂƂ̗��j������Ă����h���}�`�b�N�ȓ��e�ł�����A��������̍��͑厖���Ǝv���܂��B�Ō�́u����͒�����̗a������́v�Ƃ����L�[���[�h���A�O���̃T�r�̃����f�B�������Ƃ��Ă��܂����A�r������ς���Ă��܂��܂��B���������f�B�����`�ʼn��삵���ق����ЂƂ̋ȂƂ��Ă̂܂Ƃ܂肪�o��̂ł́A�Ǝv���܂��B�ڂ��Ȃ�A�����������Ƃ����̂͂���̂ł����A�E�E�E�B
�S�P�@����I��冋o�������Ƃڂ��灄�o�D�X�W
�h�F���X�����̎��ł��B�����ƌ��錾�t������߂��Ă��܂��u�����������ׂ�������ɂ����āv�u�ق����Ȃłāv���A���������������疟�ł��B������ɉ���`�������̂��m�ɂ��邱�Ƃ���ł��B
�n�F�Ȃ̓W�J���_���_���Ƃ��Ă��āA�����n�����Ȃ��B������A�CB�CC�Ƃ���3�̎�肪8����������̂Ƃ������ʂ������̂ɂȂ��Ă��邽�߂ŁA�����ƃR���g���X�g��t���Ă����K�v������B����͍�Ȃ̑��̉ۑ�ł����邪�A������ʂƂ��ẮA��͂肱�̎����\�����悤�Ƃ��Ă�����̂��A�����܂��ȂƂ���ɂ��ӔC������Ǝv���B
�r�F�l�����u�ڂ��v�̖ڂł���₩�ɑO�����ɂƂ炦�A�u�����v�ɑ������������ȓN�w�ɋ������܂����B��܂���܂����B
�s�l�F�A�R���t�������Ă��܂��ˁB�f���G�b�g�������ł��������ł������Ă݂����Ȃł��B�u�ڂ��̌��t���@�N�ɓ͂��@�������ς�邩�ȁv�Ƃ������Ƃ́A�����ɉ�����ς������N������Ƃ������Ƃł���ˁB�������܂��B
�s�x�F�ʔ������͋C�̉̂��ȂƁA���S���Ȃ��璮���Ă��܂����B���ɂT�R�A�T�S���߁A�u�l������ɁA�����悤�܂܂Ɂv�̃����f�B���D���ł��B�P�V���߂P�W���߂̕����������Q���ɂȂ�̂ł����A�Ȃ����������Ȃ̂��^��͎c��܂��B���ɂ��Q�l�ʼn̂������������Ă������̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�g�F���t���������ł͉̎��������f�B�[���悭�킩��Ȃ������B�����Ȃ�����ȂɗD�����v���̂��ӂꂽ�̂Ȃ̂�����A���̎v���������Ɠ`���悤�ɉ̂��Ăق����B�h
�e�F�V�N�ȏՌ��A�Ƃ��������ł��B�A�R�����ł̃f���G�b�g�A����Ȃ����́A�����f�B�Ǝ��̃I���W�i���e�B������A�䂫�����܂��B�e���r�h���}�̑}���̂��e�[�}�\���O�̂悤�ȕ��͋C������܂��ˁB�S�̂̍\���ł����A�u���ނ��`�v�̂`�����ƁA�u���珬���`�v�̂a�����ɁA����Ɂu���́`�v�̂b�����i���ꂪ��ۓI�ȃT�r�j�łł��Ă��܂����A������Ƃ܂Ƃ܂肫��Ȃ������ł��B�����܂��ȕ��͋C�������̂�������܂��A�a�������g�킸�A�`�����̂܂܂a���������������āA���̂��ƂŁu���́`�v�Ƃ����A�Ō�͂Ƃ��Ă��V�N�ȃC���[�W�ɂȂ�Ǝv���̂ł����A�ǂ��ł��傤�H
�S�Q�@��������������m�ԁ��o�D�P�O�P
�h�F�����錈�ӁA�v���𐅔m�Ԃ̋C���������p�ɂ������āA�V���v���ɏ��ɂ܂Ƃ߂Ă��܂��B�u��������킹�ċF��V�g�v���m�Ԃ̎p�������ɕ\�����Ă��܂��B
�n�F�����̉��t�ŁA�s�A�m���t�̉��ʂ��̂�������͂邩�ɑ傫���������߁A��₤�邳��������ꂽ���A�Ȏ��̂͂ƂĂ��ǂ��B���͂��������������K�v�ȂƂ�������邪�A�u�����Ɓ`�����čs����������v�Ƃ����t���[�Y���A�̂���̎咣�Ƃ��ăX�g���[�g�ɓ`����Ă���Ȃ̂���ɂȂ��Ă��āA�V���v���������̂���̂ɂȂ��Ă���B
�r�F���肵���Ȃɂ������Ɩ��키���Ƃ��ł��܂��B�p�Ɠ�������ۓI�ɕ�����ł����܂��B�ȂƎ��̑����������ł��ˁB
�s�l�F���m�Ԃ̃C���[�W���Ȓ��ɂ҂�����ł��ˁB9���ߖڂ���̃T�r�ւ̓�����6���߂��A��ۓI�ȃT�r�́u�����Ƃ₳�����`�v�̕����ɁA�����ƍ��܂�Ȃ���A�����Ƃ킭�킭���Ȃ���Ȃ����Ă��������C�����܂��B
�s�x�F�R�s�ڂ̐��m�Ԃ̌J��Ԃ��̃����f�B�����Ɉ�ۓI�ł��B�S�̂̍\��������ƁA�O���������悤�ȉ��^�ŁA�����u���������v���Ă��銴�������Ă��܂������A�u�����Ƃ₳���������Ă䂫�����v�̏����ƍl����A�����͂Ȃ��C�����Ă��܂����B�����A�u����[�v�łS���L�����̘a����D�Ȃ̂͂ǂ��ł��傤���H��╽�ɂȂ�̂ŁA���̉\�������邩������܂���B
�g�F�����Ƃ�ƐS�ɂ��݂�́B�㔼�̐���オ��u�����Ƃ₳���������čs����������v�̂Ƃ���͂����ɉ����炸�ɂ���������Ɛ���オ�����܂܂ŕ����Ă������Ǝv��
�e�F�Â��șz�Ƃ������͋C�̏�i���A���̂܂܂ɐÂ��ɉ̂��グ�Ă��܂��B���ԕ��́u���Ȃ��̐S�̗D���������ɉ������v�����s��������������Ă��܂��̂ŁA���������Ȃ��A�Ɗ����܂��B������Em��E�̉��̕t�߂����܂���Ă��܂��̂ŁA�P���ɕ�������̂ł��傤�B
�S�R�@�T���V���C���@�V�X�^�[�Y�ƒ��ԒB���T���V���C���@�V�X�^�[�Y���o�D�X�U
�h�F���[���A�̃Z���X���Q�̌���ł��B���ꂼ���̃G�X�v���I�@�O�l�o�����������̂Ŏ��Ƀ��A���ł��B�u���Ȃ��N���H�v���āE�E�E�E�v�̘A���Ƃ�킯�ʔ����ł��B����̕��������������ł��܂��B���̉i��������ɂ���̂����߂Ēm��܂����i���������A�ɂ�����ǂ������Ă�Ƃ���v���Ă܂����j�B��������҂��Ă܂��B
�n�F�Ȃ�����������慎h�Ǝ��}�������ɗZ�����Ă��āA�ɉ��Ȗ��̉���B���t���A���Ƀs�A�m���t�̌����ȃT�|�[�g�������āA�����Ă��Ċy��������ɂȂ��Ă����B���������X�^�C���̉̂������Ƃ������܂�Ă��ǂ��Ǝv���B
�r�F�e�ރ��Y���A�x��B���C���ӂ��̏��B�y�����̂��p�B�O�o���ɔ���B
�s�l�F�D���ł��A���̊����B�쎌���T���V���C���V�X�^�[�Y�Ȃ�ł��ˁB3�l�̉�b�̒����炱�̎������܂ꂽ��ʂ�z�����邾���Ŋy�����Ȃ��Ă��܂��B���̉̂ɂƂǂ܂炸�A���̒��̂����ȃf�^�����Ȃ��Ƃ���̂������̂̂�Ɠ˂����݂ł���������Ă����Ăق����ł��B���N���݂����Ȃ��B
�s�x�F���ЂƂ��K�s���Ȋ��������܂������A�y�������t�ł����B�����f�B�������Ă��Ă��Ă��ł����A�̎����ǂ��ł��Ă��܂��B
�g�F�����Ȃ��̂��ʔ����I�y�����čō��I
�e�F�u�x�炫�Ńf�r���[�̎O�o���v�u���{�[�ł��B�����Ȃ����t������ł��B�u�܂͏Ί�̌��铹�v�u�݂�Ȏ��F�̍��Y�v�u�킭�킭�����ā@�ǂ��ǂ������āv�Ȃǂ̕\���Ɖ�����y�����������܂��āA�G���^�[�e�C�������g�Ƃ��Ă��听���B�ǂ�ǂ�n��̂��Ăق����Ɗ��҂��Ă��܂��B
�S�S�@�a��s�E�J���������T�[�N���Ђ������_���l�Ƃ��ā��o�D�P�O�Q
�h�F�V���v���ŗ͋����̎��ł��B���s�E�J�����T�T�l�̕��肪�`����Ă��܂��B�u���肬��v�Ƃ����\�����������������Ȃ������̂ł����A�̂��ƋC�ɂȂ�܂���ł����B�����̌��t��s���������A���肬��̂ƈꌾ�ŕ\�������ق����悭������܂��B
�n�F�����̂Ȃ��Ő��܂ꂽ�ȂƂ��āA�X�g���[�g�ɔ����Ă�����̂�����B���̑O�������̐������ƂĂ������B�T�r�ɂ����镔���́u�l�Ƃ��ĂĂ䂸��Ȃ����̂�����v���A����͓����̉��t�ɂ���邪�A���������ω��̂�������ɂȂ��Ă���ƁA����Ɉ�ۂ������Ȃ�Ǝv����B�܂�A���̋ȑS�̂�8����������̂Ƃ��������ɏI�n���Ă���A�����̊g��≹��̍L��������Ă����K�v������̂ł͂Ȃ����B
�r�F�͋�����ɖ�������܂����B����Ԃ����d�w�I�ɏ�����߂Ă䂫�܂��B
�s�l�F�Z���t���[�Y�ɂ�������炸�A�����Ȍ��i���ڂɕ����т܂��B���̗͂��������Ƃ��炽�߂Ďv�킳��܂��B�����ɋ����ƂƂ��Ɉꏏ�ɉ̂������Ǝv�킹�郁���f�B�B���t���I��������A�����ƈ����Ă��������قǂ��A�A�т̔����܂����B
�s�x�F�̂��₷�����R�ŁA�悭�ł��Ă��邢���̂��Ǝv���܂��B���t���ǂ������B���c���y�̖��͂����Ă��ĐS�Ɏc�郁���f�B�ł��ˁB
�g�F����Ȃ��^�������Ȍ��t���S�ɐ[���`����Ă���B�v�����߂ĉ̂���f���炵�����e�FWe
shall overcome �Ƃ��Ԃ点�āA�L����̂��锭�z������܂��B�����Ă��Ԃ���U��グ��̂ł͂Ȃ��A�g�����s���Ƌ��ɑ傫�ȋ��������邽�߂̎���Ȃ��̂ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B�ق�Ƃ̋�����\���Ă��܂��ˁB
�S�T�@�o�J�{���Y&�Ԃӂ�o���h�����{�����������������s�������������T�[�N����For You���o�D�X�S
�h�F�y���ȃ��Y���̊y�����̂ł��ˁB���̂悤�ȃm���̋Ȃɂ́A�����|����̂��錾�t�A������錾�t�͂Ȃ��܂Ȃ��̂�������܂���ˁB�l�Ɛl�̂Ȃ���̒��ň��ł������̂��A�P���ȃt���[�Y���J��Ԃ����ʓI�ɓ`���Ă��܂��B�@
�n�F���܂��܂Ȋy���������āA���₩�ȉ��t�̕���ƂȂ����ȁB���̋Ȃň�Ԉ�ۂɎc��̂̓��t���C���́u�l�ƒm�荇���^�l�ƌ�肠���`�v�̂Ƃ���B���C�ɂ��ӂꂽ�ȁB�����܂ł̉��y���A����M�����̂悤�ȁA���̎ア�����f�B���C���ɂȂ��Ă����̂��ɂ��܂��B
�r�F�ԑt�����t���Ԍ������Ă��܂��ˁB�s���̒��ɂ�������������Ɉ�����銈�����A���̋Ȃ̔��͂��x���Ă���̂ł��傤�ˁB����40���N�̔N�ւ����t�ɍ��߂��Ă��܂����B
�s�l�F���[���Ɖ̂������Ă������Ƃ̏W�听�����̉̂ȂƂ������Ƃ��悭�킩��܂��B�y�����Ă����������Č��C���o�܂��ˁB�W���Y�̉��t���f�G�ł����B
�s�x�F�̂ɉ�����A�L�т₩�őu�₩�ŁA�l���������ޗ͂̂��邢���̂ł��B�ԑt���H�v����Ă��Ċy�������t�ł����B������x���������A�����̂������̂ł��B
�g�F���邭�z�C�ŗD�����S����ł����f�G�ȋȁB���肩����(��)�ɓ���O�̐L������������ƂЂ�������̂�������d�B
�e�F�y�����o���h�ƃq�b�g���h���[�ł�����������オ��܂����B�l�Ɛl�̂Ȃ��肪�����錴�_�A�����̂��Ǝv���܂��B�����A�P�́u���̗���`�v�ł͂��܂郁���f�B�ɁA�����Q�́u�����Ȃ��`�v�̃����f�B�����Ď����R�ɂ܂��Ⴄ���������āA������Ƃ܂Ƃ܂肪�Ȃ����������Ȃ��A�Ǝv���܂��B�S�́u�l�ƒm�荇���`�v���炪��Ԃ����Ƃ���Ȃ̂ŁA�����܂łł��邾���P�̃��`�[�t��厖�ɂ����\���ɂ���ƎU���Ȋ������Ȃ��Ȃ�A�Ђ����܂��Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�S�U�@�����s�������������T�[�N�������̒��Ł��o�D�X�R
�h�F����������̎��ł��B���̒��Ƃ́A�����������ꂼ��ɕ�炷���Ȃ̂�������Ȃ��ł��ˁB����ȃC�}�W�l�[�V�������������Ă�̎��ł��B�u�Ȃɂ��Ȃ����v�ƌ������Ȃ��ŁA���̎p�������ė~�����ł��B
�n�F�t�H�[�N�\���O�̃X�^�C���ɂ�鍇���ł̉��t�͂��Ȃ蔗�͂��������B�Ȏ��̂͂��������X�^�C���̓��������������A�y���ŗ����ȌĂт����ɂ��ӂ�Ă��邪�A���̓��e������߂Ĉ�ʓI�ŁA�ǂ��̒��ł������킯�ŁA�̂�������̌��I�ȕ\������Ă��Ȃ��B�u���̒����D���v�Ƃ������傪�����̂Ȃ��f��ɂȂ��Ă���킯�ŁA�����Ƌ�̓I�ȓ��e��\������K�v������Ǝv����B
�r�F�y���Łu�q�ǂ��������l�Ԃ炵�������Ă������߂Ɂv�B�匠�ݖ��B���̂Ђт����₳�������ɖ����܂����B�u�킽�������̒������낤�v�Ђ낪��̂���e�[�}�ł��ˁB
�s�l�F���̂����I�������ꂽ���t�Ɖ̏��ł����ꏏ�Ɍ������݂����Ȃ�̂ł��ˁB�ԑt�������ł��ˁB�C�x���g�Ȃł͒Z��������ׂ�������ꂻ���ł��ˁB
�s�x�F�悭�܂Ƃ܂��Ă��āA�e���݂₷�������̂ł��ˁB�̂����t�����炵���ł��B�����A���̃e�[�}�͊e�n�ɂ�������̂ŁA�����Ƒ��́u�킽���̂܂��v�Ȃ�ł͂̂��̂��o�ꂵ�Ă������̂��ȁA�Ƃ��v���܂����B
�g�F�y���ł���₩�ȋȁB�̎�������ʓI�Ȉ�ہB
�e�F�̂��₷���܂Ƃ܂�̂���f�G�ȋȂł��B�������ꑱ���Ă��闝�R���킩��܂��B
�S�V�@���m�q�ǂ��̍K���ƕ��a���肤�����c�{�e�Ǝq�݂̂ǂ�̓m�����c�����̂ӂ邳�Ƃ����o�D�V�W
�h�F�����Ă��܂����̋��ɂ悹��ɐȎv����\�������A�ƂĂ�������₷���A�����ł���̎��ł��ˁB�~���[�W�J���̌����̂Ƃ��đ��݊��̂����i�ł��B
�n�F�m���������̍D��������A��ۂ̋�������ƂȂ����ȁB�~���[�W�J���̂Ȃ���1�ȂŁA�\���ƍ����Ƃ̑g�ݍ��킹�œW�J����Ă���A���̓I�ȍ\��������������B�e�L�X�g�����q�I�ȃX�^�C���ł��邽�߁A�Ȏ��̂�����ɉ������`�ɂȂ��Ă��邪�A���������]�C�����������镔���������Ă��ǂ������悤�Ɏv��ꂽ�B���������Ȃ͂�͂蕑��őS�̂�ʂ��Ē����Ă݂�K�v������Ǝv���B
�r�F�悢���b�Z�[�W���̏��̖����ꂽ���t�B�q�ǂ��̒��ڌ�@�ɋ������܂����B
�s�l�F����e�[�}���l���q���������ł��镑��ɍ��ꂽ�F����Ɍh�ӂ�\���܂��B�����������߂łƂ��������܂��B���̎q�̃\���A�ƂĂ��f�G�ł����B
�s�x�F�O���̕`�ʁA�㔼�T�P���߂���̔����������f�B�A�V�U���߂���́A���ꂪ���͓͂��Ȃ��ꏊ�ɍs���Ă��܂��Ă��邱�Ƃ̔߂��݂Ƒi���A���ׂĂ̕��������J�ɁA���y�I�ɂ��ǂ�����Ă��āA���炵����i���Ǝv���܂��B�q�ǂ������̉��t���ƂĂ��ǂ������ł��B�u���{�[�ł��B
�g�F�u�~��悤�Ȑ���v�ƓW�J���Ă����Ƃ��낪�f���炵���B
�e�F��҂ɂ���
�S�W�@���m�q�ǂ��̍K���ƕ��a���肤�����c�{�e�Ǝq�݂̂ǂ�̓m�����c���������Ȃ��́��o�D�W�S
�h�F�G���f�B���O�e�[�}�̂��̍�i�́A�P�Ƃł��̂��L�܂�͂�����������x�̍�����i�ł��B�V���v���ł��邪�̂ɑ�Ȃ��Ƃ���������`���Ă�����ł��B�Q�Ԃ́u���ӂ�ʼn̂�������̂ւ��ȉ̂��D���ł��v�͋������܂��B�����̌������̖̂����A�X�s�[�f�B�[�ɕ�����₷���`���Ă����B�����o���҂��y�������t���Ă���͎̂Ă̑����y�����Ȃ�܂��B�~���[�W�J���d���ĂƂ�����̉\�����������Ă���Ǝv���܂��B
�n�F�t�W�����E�A���O���Ƃ����ׂ��y���ȃ��Y���ɏ���ēW�J�����Ȃ����A���̌y�����̂Ȃ��Ɏ��̂Ȃ��݂���▄�v���Ă���悤�Ȉ�ۂ���B�u����ӂ邳�Ƃ��v�ł��������悤�ɁA�~���[�W�J���̒��̋Ȃ́A��͂�{���I�ɂ͂��̕���S�̂�ʂ��Ē����K�v������킯�����A�����������Y�~�J���ȋȂ̏ꍇ�A���t���鑤�����̃��Y���̐S�n�悳�Ɉ��Z���Ȃ����Ƃ��K�v�ł͂Ȃ����B
�r�F�����̂���ȂɑS�g����̂����|�I�ȉ̂̎��͂������܂����B
�s�l�F���̉��t���������ł������Ȃ��̂���邽�߂ɂ͂���ς茴���͂���Ȃ���ˁA�Ƃ������Ƃ��z���ł��܂��B�������Ă���F����̕\���p�����\���Ȑ����͂�����܂����B�����͂��̃~���[�W�J�����ς����Ƃ����v���ɋ���Ă��܂��B
�s�x�F������܂��̂��Ƃ��ǂꂾ���K���������̂����A�S�ɐ[�����܂����̂ł��B�悭�ł��Ă��܂��B���̃~���[�W�J�������Ќ������Ǝv���܂��B
�g�F���邭�Čy���ŗǂ��̂�����ǁA���e�⎌���l�����Ƃ��A�s�A�m���t�̃��Y�������܂�Ɋy�V�I�߂��͂��Ȃ����낤���B
�e�F��҂ɂ���
�S�X�@�e�J�����{���m�̂��������������̓V�C��b���悤�Ɂ��o�D�V�V
�h�F�쎌�Җ{�l�̂��ߍu�]�Ȃ�
�n�F����̕�炵�Ƃ������_���畂���яオ�邩�������̂Ȃ����̂��A�D��������Ă��鎍�����A�O���̋Ȃ̓W�J����₭�ǂ��B�T�r�̕����̐����W�J�͂ƂĂ����R�ŁA���ɃR�[���X�̋����Ƃ����܂��ĖL���ȍL��������������邪�A���t���C���̐��������������I���@�ɂȂ��Ă��Ă�╽�B���̕����������ƈ�ۓI�ȃG���f�B���O�ɂȂ�ƁA�ȑS�̂������ƈ������܂�Ǝv����B
�r�F���}�ȕ�炵�̒��ɂ���l�̐S�ƐS�̐G�ꂠ���A�ӂ肩�Ԃ����X���[�K�������D�����������́B�Â��Ȑg�߂ȁA�����Y�ꂪ���Ȃ��Ƃւ̐V�N�Ȑ�������܂����B���炵���̏��B
�s�l�F�����̓V�C���͂Ȃ��悤�ɒW�X�Ƃ����Ȓ����ӎ����ꂽ�̂��Ǝv���܂����A�t�ɂ��̂��Ƃ��َ��ȕ��͋C�����������錋�ʂɂȂ��Ă��܂��Ă��܂��B�T�r�́u������b������`�b������v�f�G�ȃ����f�B�Ȃ̂ɁA�Ō�́u�����̓V�C���i�e�j�b���悤�i�b���j�Ɂv�Ń\���O�łȂ��Ȃ��Ă��܂��Ă���悤�ȋC�����܂��B
�s�x�F�Ɠ��̗]�C�̎c���i�ŁA�����Q�l�ɂȂ�܂����BF��C#��C�̓������Ȃ��Ȃ����Ă��ł��ˁB�Q�J�b�R����̓ˑR��Eb�̓o����������낢�ł��B�u������܂��v�Ƃ����̎��Ȃ̂ɁA���͂�����܂��ł͂Ȃ��̂ł��ˁB�I��������ې[���ł��B
�g�F�㔼�́u������b������v���炪�ƂĂ��X�e�L���B�I���̕��u������܂��̕�炵�̒��Łv�̂Ƃ���A�����ƕ��ʂ��ۂ��Ă��ǂ��̂ł͂Ȃ����B���g���Ă���a���ƃ����f�B�[�ōs�������Ȃ炻�̌�ɂ����Ɗ�ȓW�J���~�����B
�e�F�O���̎���ǂނƁA�ڂ��������郁���f�B�͂������������̏��Ȃ����̂ł��B�u������E�E�E�v����͂��̋Ȃɂ҂����肾�Ǝv���܂��B�^�C�g���ł�����u�����̓V�C��b���悤�Ɂv�̃R�[�h�A�H�v���Ă��܂��B���������Ȃ����A�����Ȃ��Ƃ�����������悤�Ȋ܂݂̂���\���ɂȂ��Ă��܂��B
�T�O�@���̂����͂����ݕ��a���˂��������c���큄�o�D�V�U
�h�F�f���Ő����͂̂��ӂ��̎��ł��B�悭�܂Ƃ܂����G��ȍ�i�ł��B�P�A�Q�ԂƓW�J���ĂR�Ԃłǂ�Ȃ��ꂢ�ȉԂ��炭���Ǝv������A�L���E�����Ȃ����Ƃ����ӊO�����V�N�ł����B�ǂ�Ȏ�Ȃ̂��ӂꂽ������Ɗy�����Ȃ肻���ł��ˁB�i��F�S�}�݂����ɍ����Ă������Ⴂ�B�@���Ŕ���ꂻ���@���j
�n�F�Ȃ��ƂĂ��V���v���ŁA�ƂĂ����������Ă����́B���ɖ`���́u��������ς��^�܂��܂����v�̐����������B�������w�̂悤�ȗD�����ƃ��N���N���������āA������Ȃ������ɕ`���o���Ă��āA�ƂĂ������B���������Ȃ̍��������ƎQ�l�ɂ���K�v������Ǝv����B
�r�F�܂������Ƀe�[�}�ɂނ����u��v�B��]�Ɖ\���Ɋ�B�����ɂ́u�҂v���Ԃ�����B
�s�l�F�y�����ł��B�j�����u�o�Ă����`�v�Əo�Ă���Ƃ���A�u��������I�I�v�̊����Ȃ������ł��ˁB�u���N���N�v�u���킻��v�u�������������v�͖{���ɋC������\���Ă��܂���ˁB���ʓI�ȃt���[�Y���Ǝv���܂��B
�s�x�F���킢�炵���āA���Ă��ȉ̂��ł��܂����ˁB�����f�B�̂������A���Ƃɂ҂�����ł��B�x�݂Ȃ��u�łĂ����[�v�Ƃ����ɏo�Ă���Ƃ���́A�肪����o�����������ǂ�����Ă��܂��B�肪�o�Ă����L���[���̎킪�ǂ�ǂ�L�тčs���̂��A���x�͂��Ѝ���Ă��������B���t�E�A�����W�����Ă��ł����B
�g�F�e���݂₷���y���̂������������������Ă����́B�u�o�Ă����@�o�Ă����v�ƌ����t���[�Y�ƌ��t���ʔ����B
�e�F���邭���Y�~�J���ȉ̂������͑f�G�ł��B�P��ڂ̃��N���N�A�\���\���A���������Ƃ������[���ɑ��郁���f�B�͂��̋Ȃ̒��̃`���[�~���O�ȃ|�C���g�ɂȂ镔���Ȃ̂ŁA�y�����Ȃ�H�v������Ƃ����ł��ˁB�܂��A�u�����������v����u�łĂ�����v�̎n�܂肪��ϋ����ɂȂ����Ă��邱�Ƃ́A�Ƃ��Ă����������Ȃ��Ǝv���܂��B�u�����������v�ŗ]�T�̂���I�~�`�ɂ����Ă����āA���炽�߂āu�łĂ�����v�����ۓI�ȃT�r�̕����Ƃ��Đ���グ�邩�A�Ȃɂ��H�v������Ǝv���܂��B���ڂɏo�Ă��郏�N���N�A�E�E�E�Ȃǂ��ԉ��т��Ă��܂��Ă���̂ŁA���̂ł����i�K�ł͂������N���N�ł͂Ȃ��A��������t�̂ق��������̂ł́A�Ǝv���܂��B�������ł��傤���H
�T�P�@�����c�Ȃ��܁��l�Ԃ��Ă�����Ȃ����o�D�W�U
�h�F�N�ւ�����ł����l�łȂ���Ώ����Ȃ��A���̂���̎��ł��B�u�قǂقǂȂ�Ƃ������Ă����v�T�����ƐS�����̎��ł��B�R�ԁu���Ƃ��Ȃ������`�O�����������ł����v�̕����͎�̎����킩��Â炢�ł��B�u�铹�ŋȂ����Ă��čs������͂�ł�����O�͌����v�Ɨ������̎��͍l���Ă��܂��܂��B
�n�F�Ȃ̃X�^�C�������̕��ŁA���̃p�^�[���P���ċȂ��W�J����Ă��邪�A�����Ȃ�Ǝ��̓��e�������͂̂Ȃ���̂��ǂ������J�M�ƂȂ�B���̓_�A�^�C�g���ɂ���u�l�Ԃ��Ă�����Ȃ��v����₱�����������������鎍�̓��e�ł���̂��c�O�ł���B
�r�F�u�����̎����ɏo��v-�f�G�Ȍ��t�Ɂh�����h�g�����h���܂����B�����Ƃ��Ѝ��Ԃ炸�l�����Ǝ˂���p���ɏn�N�̖����݂܂����B
�s�l�F���̕��͋C��D���ł��B�u�u�������̂��v�Ƃ����Ԃ��ā@�����Ɨ܂��������@����̏d���Ƃ��͂Ȃv���̃t���[�Y�ɂ͂��т�܂��B���̒��̉̂̂��Ԃ��̉�ȂǁA�����ɂ���Ƃ��ɂȂ��Ȃ���ςł���ˁB�̎��t���Ȃ���ς������肵�܂����A1�Ԃ�2�Ԃ�������ƃ����f�B���������̎����肪������肷��̂͂��̎�̉̂̏ꍇ���邱�ƂȂ̂ŁA���߂�t�����肵�Ă����Ƃ����Ǝv���܂��B�Ō�́u�������̕��������ā@�����̎����ɏo��v�����܂��I�@
�s�x�F�����e�[�}�ł������͋C�̉̂ŁA�p�[�c�����o���Ƃǂ������͓I�Ȃ̂ł����A�S�̂�����ƍ��ЂƂ�ۂ������̂͂Ȃ��Ȃ̂��낤���ƍl���Ă݂܂����B���Ƃ��A�ŏ��́u�������́v�u�������́v�u���傤�́v�̃����f�B���R��Ƃ��������ŁA�����a���Ȃ̂͂ǂ��ł��傤���H���Ƃ�����Ȃ��Ƃ��l�����邩�Ǝv���܂����B�i����V�j
�g�F�l�������������Ă���閡�킢�̂���́B�R���ߖځE�S���ߖڂɏ����ω����~�����B
�e�F�N�̌��A���킢�[���̂ł����B�o�������Ȃ��Ȃ����ł��B�̂̃^�C�g���ł���u�l�Ԃ��Ă�����Ȃ��v�Ƃ����Ō�̕������ق�Ƃ̓N���C�}�b�N�X�ɂȂ��Ăق����Ǝv���܂����̂ŁA�����������ƃ����f�B�̊W������Ƃ����Ǝ��̒��g���X�g���[�g�ɓ����Ă���̂ɂȂ�Ǝv���܂��B
�T�Q�@���É��N�����c�����̊w�Z�W�U���L�u���[�Ă��с��o�D�W�V
�h�F��ɕx�̎��ł��B�V���v���Ȍ��t�ŖL�`�Ȑ��E��\�����Ă��܂��B�P�Ԃ̍Ō�A�u�����������������Ă����v���܂��I�̈ꌾ�ł��B�^���Ԃ����A�Ƃ������t���������錾�t�ł��ˁB
�n�F�g�䂤�Ђ��܂��������h�̃��Y���Ɛ������f�G�B���ꂪ�����ナ�t���C���̖������ʂ����Ă���A���̂��Ƃ̐�����]�C�[�������ɗU���Ă���B������5�����K�ӂ��ɓW�J����Ă��āA������ӓ|�łȂ��̂������B��ې[���ȁB
�r�F4�s���u�[�Ă��сv�͎��ԁi�[���j�Ə�i��I�m�ɐ����Ă��܂��B����Ԃ����킸��킵���Ȃ�������߂Ă��܂��B
�s�l�F�c�����̉̎������邾���ł��[�Ă��ƂƂ��ɉ̂������Ă���悤�ł��B����Ɓu�Ɏq�v�Ƃ��u�p�_�v�Ƃ��u�`�āv�ȂǕ��i���܂�g��Ȃ��������g���Ă���Ƃ�����Ȃm�X�^���W�b�N�Ȃ��̂����������܂��ˁB
�s�x�F�����̂̎q�ǂ�������������v���o���悤�ȁA�O�荂�����ɂ҂�����́A�����Ƃ肵�������f�B�����Ă���ǂ���i���Ǝv���܂����B�悭�܂Ƃ܂��Ă��܂��B
�g�F���{�I�ȏ�A��т��т����������Ă����悭����ꂽ�ȁB���R�W���̍�i���v�킹��B�u�܂��������v�̂Ƃ��낪���Ɉ�ۓI�B
�e�F�����̂ł��ˁB�m��܂���ł����B���������i�Ɖ������������A�t���[�Y�̏����Ȃǃv�����݂̏o���h�����Ǝv���܂��B�L���݂Ȃ���ɉ̂��Ă��炦��悤�ȏ��̂ɂȂ�Ǝv���܂��B�P�̊y���łP�`�R�Ԃ܂ŏ������`�ɂ��đO�t�Ȃǂ��ȒP�ɏ������猩�₷���Ȃ��čL����̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�T�R�@���É��N�����c�{���m�̂����������W���S���͉̂����o�D�W�T
�h�F�@�������������@�����@���������̂���{�̂悤�ȉ̎��ł��B������₷���A�͋����̎��łЂ������܂��B�쎌�̉i�䂳��͖k�C���ɂ��Z���̕��ƕ����܂����A�܂��ɊC�͂Ȃ���A�����ЂƂ̒n���Ɏv�������̂ł��B
�n�F�C���g���ʼn̂��郊�t���C���̃p�b�Z�[�W���V���v���łƂĂ������B���C���̐����̉��悪��r�I�����͈͂œW�J����Ă��āA���������L����̂�������ɂȂ��Ă����ق����悢�̂ł́A�Ǝv��ꂽ�B���̓V���v���Ŗ����ŁA�悭�`����Ă�����̂�����B
�r�F�u���炤�݁v�̐߂܂ł̃W���S���̎p�Ԃ������ԁB�u�Ԃ�����v���v���o���܂����B�������܂������̂ł��ˁB
�s�l�F�����t���[�Y�����x���J��Ԃ���邱�Ƃ͂Ƃ�����ƖO���Ă���̂ł����A���͍̉̂L����ɂȂ��Ă���S�n�悳������܂��B���̍L���肪�����ɕς��܂�����ɍL��������܂��B���g��ł����������̂ł��ˁB�i���������ŋߌ��g��ł��������Ƃ��Ȃ��Ȃ����Ȃ��j
�s�x�F�̂̈Ӗ��Ǝ咣���͂����肵�Ă��āA�������Y����Ȃ��悤�Ȉ�ې[���̂ł��B�㔼�̌J��Ԃ��̕����͊o���₷���ł����A�L�����������ʼn̂������ł��ˁB
�g�F�咣�̂͂����肵���킩��₷���́B
�e�F��҂ɂ���
�T�S�@���É��N�����c�{���m�̂��������{���c�`�Y�������܂����o�D�W�W
�h�F�쎌�Җ{�l�̂��ߍu�]�Ȃ�
�n�F���Y�~�J���Ō��C���ӂ��́B�Ȗ{�̂��f�G�����ASing
Out �ł̑O�t�ƌ�t���傫�Ȑ���オ���n�肾���Ă��đf���炵���Ȃ̗͂������������B
�r�F�u����Ƃ�ǂ�ɂЂ炫�܂��悤�Ɂv-���́u����Ƃ�ǂ�v�ɍD���������܂��B�ǂ�������F�A���������Ȃ��ƕs���A�Ƃ����X��������܂�����ˁB�e�ރ����f�B�A���邢���X�A�܂��Ɂu����Ƃ�ǂ�v�ł��B
�s�l�F���̃C���[�W�ƋȂ��҂�����̖��Ȃł��B�����������߂����ȉ̂ł��ˁB�Ō�́u����Ƃ�ǂ�Ɂ`�v�́u��Ɂ`�v�̂Ƃ��낪������Ɗo���Â炢�ł��傤���B����������Ə�̉���ł��悩�������Ȃ��Ǝv���܂�����͈̔͂ł��B���m�ՓT�̑升�����y���݂ł��B
�s�x�F�̂��₷���āA�i�������āA�͂������āA��]�Ɉ��Ă���ǂ��̂ł��B�ō�����C#�ł����A��ӏ��A���Ƃ��u�傫���v�Ƃ��A�u����Ƃ�ǂ�v�̂�����ŁAE��D#�܂ŏオ���Ă������悤�ȋC�����܂��B�֑��ł����B
�g�F�o���ɂ��p�X
�e�F�V���v���Ń��Y���̂���̎����A���������Ƃ����͂̂���̂������o�����Ǝv���܂��B�q�b�g���[�J�[�̂���l�炵����i�ł����B
�T�T�@�R�����q���G�莆���ꁄ�o�D�P�Q�Q
�h�F�D���x�̍�����i�ł��B�������������������I�Ȃ̂��C�ɂȂ�܂��i�Q�A�R�Ԃ̏o�����̕������j�B������̓��̒��Ɋ������̊G�莆���L�����Ă������Ƃ��C���[�W���ė~�����ł��A�����A�킩��ɂ����H�u�Ԃ�ʕ��v�Ə����̂ł͂Ȃ��u���̃i�X�r�v�u�����炢������v�ȂNj�̓I�C���[�W��[�߂���\���ɂ��邱�Ƃł��B�S�̔����S�J���邱�ƂȂǂ͏����Ȃ��ē`���܂��B������̃C�}�W�l�[�V�����̗͂�M�����Ă��������B
�n�F�����̓W�J���ƂĂ����R�ŁA�����̉��t���Ȃ��Ȃ��悭�A��ۂɎc�����ȁB���ɃT�r�̕����̐����̍ŏ��̃t���[�Y���傫�ȍL�����������������̂ŁA�ƂĂ��������A���̂��Ƃ���₵�ڂ�ł��܂��B����͎��̓W�J����⋷���A�u�G�莆�v�ɂȂ�����̂��\���ɕ\������ĂȂ����炾�Ǝv����B
�r�F�u���܂˂��v�u�Ԃ�ʕ��v�Ȃǃ��m�����B�u����͎��̐S�ɏo���������G�莆�v�ƒ��ۓI�łȂ��A��A��A�O�A�Ɣ��W���Ă䂭�B�\���̖��������܂����B
�s�l�F���������������f�B�����ɓ͂��A���Ɏ��ɏW�����Ă݂�B����Ɓu�`���n�߂����܂˂��v�Ƃ��u�S�̔���������ƊJ���ĕ�̌��t���͂����v�A�����āu������育�������������̊G�莆�v�Ō����B����Ȃ����t���S�n�悭�g�̂ɓ����Ă��܂��B
�s�x�F�悭�܂Ƃ܂��Ă��邾���ł͂Ȃ��A�i����͂ƋC�i�̂��邢���̂ł��B�܂��A�u�v�����߂āv�u�`���グ���v�̃����f�B�̌J��Ԃ������܂��I�Ǝv���܂����B�J��Ԃ����Ƃŋ��ɔ�����̂����܂�Ă��܂��B����ꂽ���͂����Ɗ�ꂽ���Ƃł��傤�B
�g�F�M�҂͊G�莆�̂��Ƃ��ڂ����m��Ȃ��̂�����ǁA����Ȏv���ŏ������ƁA�悭�`���̂������B�e�F�D�����S�̂������������f�B�őS�̂̍\�����悭�ł��Ă��܂��B�u��́E�E�v����̃����f�B�����Ɉ�ې[�����܂��ł��Ă��܂��̂ŁA�Ō�ɂ�����x���������������Ǝv���܂����B